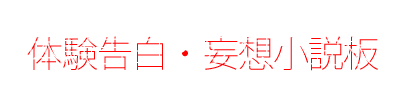
- 投稿される方は、無償且つ時間を掛けて文章を書き投稿されています。閲覧される方は、出来る限りお礼や感想(批判は×)を付けて頂けるようお願い致します。小説・体験投稿者のモチベーションを下げる返信等は削除、連投される場合はアクセス制限対応します。
- トピックの選択(特に、男性or女性、現実と妄想の区分けには御注意下さい)
- 投稿・返信は固定ハンドルネームでお願いします。
朝から男子がそわそわしている。特別な行事のないありふれた登校日だけれど、世の中的にはバレンタインデーなのだ。もしかして女子からチョコをもらえるかも……と、みんな無関心を装いつつ期待感を漂わせていた。
ボクも登校するなり机の中を確認してみたけど、残念ながらチョコを忍ばせてくれた女の子はいなかった。もらえることが確実な彼女持ちは余裕をかましている。女子がどんどん登校してくると、教室や廊下で友チョコの交換が始まった。
「……誠くん。頼んでた本が入荷したから陳列とポップ作り手伝ってくれる?」
と、結局、友チョコのおこぼれにすらあずかれないまま帰り支度をしていると、愛梨先輩が声をかけてきた。図書委員会の委員長だ。本好きのボクは一年生から司書を務めていた。
「すぐ行きます」
「みんな帰っちゃって人手が足りないの。私も用事を済ませたら図書室に行くから」
クスっと微笑んだ愛梨先輩の笑顔になにか企みを感じた。
けれど鈍感なボクは、単なる書架整理じゃないな……と確信するには経験値が足りなかった。
図書室には花凛ちゃんがいた。選択授業の音楽で一緒になる図書委員仲間だ。
肩まで伸びたセミロングはいつもさらさらで、時々結い上げていたりカチューシャを着けていたりすると、あどけない顔立ちが際立ってときめいてしまう。はっきり言って気になる女の子だった。好きな小説のジャンルがSFとティーンズラブ(TL)と共通しているのも嬉しかった。
「誠くん」
「花凛ちゃんひとりで書架整理してたの? ポップ作り大変じゃん」
「…………」
「新入荷した本どこ?」
辺りを見回しても段ボールもなにもない。ていうかポップ作りのための色ペンも画用紙もなかった。
「騙してごめん。誠くんを一人で呼びたくて嘘ついたの。愛梨先輩に協力してもらった」
「…………」
「好きです。私と付き合ってください」
頭を下げられて、顔を真っ赤に染められて大きなラッピングを差し出された。
問い返すのは野暮でしかない。バレンタインチョコでしかありえないのだ。
「あ、あ、えっと……じゃあお願いします」
数秒迷った末、ボクは手作りチョコを受け取ってお辞儀した。
なんか卒業証書の授与式みたいだね、と花凛ちゃんがボケると二人で笑った。
……帰り道、駅前のコーヒーショップに寄って初めてのデートを経験した。
テーブル席の向こうに見えるのは粉雪の舞踏会。世界中が幸福に包まれているような温かさを感じた。
「ここでチョコ食べていいのかな?」
「だめ。恥ずかしい」
「大きすぎて一日じゃ食べきれないんだけど」
「お兄ちゃんが、作る時にグラム(g)を量り間違ったから……!」
「じゃあ半分こ。ココアに入れても美味しいと思うよ」
花凛ちゃんを大切にしようと思った。
バレンタインやクリスマスに僻(ひが)まなくていい。
妄想寄稿『ユーノーの祝福 半分この帰り道』
ボクも登校するなり机の中を確認してみたけど、残念ながらチョコを忍ばせてくれた女の子はいなかった。もらえることが確実な彼女持ちは余裕をかましている。女子がどんどん登校してくると、教室や廊下で友チョコの交換が始まった。
「……誠くん。頼んでた本が入荷したから陳列とポップ作り手伝ってくれる?」
と、結局、友チョコのおこぼれにすらあずかれないまま帰り支度をしていると、愛梨先輩が声をかけてきた。図書委員会の委員長だ。本好きのボクは一年生から司書を務めていた。
「すぐ行きます」
「みんな帰っちゃって人手が足りないの。私も用事を済ませたら図書室に行くから」
クスっと微笑んだ愛梨先輩の笑顔になにか企みを感じた。
けれど鈍感なボクは、単なる書架整理じゃないな……と確信するには経験値が足りなかった。
図書室には花凛ちゃんがいた。選択授業の音楽で一緒になる図書委員仲間だ。
肩まで伸びたセミロングはいつもさらさらで、時々結い上げていたりカチューシャを着けていたりすると、あどけない顔立ちが際立ってときめいてしまう。はっきり言って気になる女の子だった。好きな小説のジャンルがSFとティーンズラブ(TL)と共通しているのも嬉しかった。
「誠くん」
「花凛ちゃんひとりで書架整理してたの? ポップ作り大変じゃん」
「…………」
「新入荷した本どこ?」
辺りを見回しても段ボールもなにもない。ていうかポップ作りのための色ペンも画用紙もなかった。
「騙してごめん。誠くんを一人で呼びたくて嘘ついたの。愛梨先輩に協力してもらった」
「…………」
「好きです。私と付き合ってください」
頭を下げられて、顔を真っ赤に染められて大きなラッピングを差し出された。
問い返すのは野暮でしかない。バレンタインチョコでしかありえないのだ。
「あ、あ、えっと……じゃあお願いします」
数秒迷った末、ボクは手作りチョコを受け取ってお辞儀した。
なんか卒業証書の授与式みたいだね、と花凛ちゃんがボケると二人で笑った。
……帰り道、駅前のコーヒーショップに寄って初めてのデートを経験した。
テーブル席の向こうに見えるのは粉雪の舞踏会。世界中が幸福に包まれているような温かさを感じた。
「ここでチョコ食べていいのかな?」
「だめ。恥ずかしい」
「大きすぎて一日じゃ食べきれないんだけど」
「お兄ちゃんが、作る時にグラム(g)を量り間違ったから……!」
「じゃあ半分こ。ココアに入れても美味しいと思うよ」
花凛ちゃんを大切にしようと思った。
バレンタインやクリスマスに僻(ひが)まなくていい。
妄想寄稿『ユーノーの祝福 半分この帰り道』
| ▼ | 妄想寄稿『間もなく電車で発射致します』 Angel Heart 25/1/31(金) 8:15 |
| Extra Episode『湯煙妄想紀行』 Angel Heart 25/1/31(金) 8:34 |
| Re:Extra Episode『湯煙妄想紀行』 純西別森木 25/1/31(金) 9:12 |
| Re:Extra Episode『湯煙妄想紀行』 Mr.774 25/2/6(木) 19:32 |
| Re:Extra Episode 純西別森木 25/2/6(木) 19:43 |
| Re:Extra Episode Angel Heart 25/2/7(金) 8:26 |
| Re:Extra Episode『湯煙妄想紀行』 Angel Heart 25/2/7(金) 7:52 |
| Re:Extra Episode『湯煙妄想紀行』 ろくべえ 25/2/8(土) 9:41 |
| Re:Extra Episode 純西別森木 25/2/8(土) 10:42 |
| Re:妄想寄稿『間もなく電車で発射致します』 純西別森木 25/1/31(金) 9:10 |
| Extra Episode『ユーノーの祝福』 Angel Heart 25/1/31(金) 17:38 |
| Re:Extra Episode『ユーノーの祝福』 純西別森木 25/1/31(金) 18:04 |
| Extra Episode『ユーノーの祝福 半分この帰り道』 Angel Heart 25/2/14(金) 18:26 | ≪ |
| Re:Extra Episode『ユーノーの祝福 半分この帰り道』 純西別森木 25/2/14(金) 19:41 |
| Extra Episode『うらすじ太郎』 Angel Heart 25/2/3(月) 18:52 |
| Re:Extra Episode『うらすじ太郎』 純西別森木 25/2/3(月) 19:14 |
| Re:Extra Episode『うらすじ太郎』 LEVEL E 25/2/4(火) 12:16 |
| Re:Extra Episode『うらすじ太郎』 純西別森木 25/2/4(火) 12:27 |
| Re:Extra Episode『うらすじ太郎』 Angel Heart 25/2/4(火) 13:39 |
235,824
禁止事項
- 誹謗・中傷・乱暴な言葉遣い
- 無神経なage行為・過度な連続投稿
- 対象者の名誉を傷つけるスキャンダル等
- 個人が特定できるような地域情報
- 18歳未満を対象とした(成人が未成年を相手にする犯罪に該当する)告白投稿
- 出会いを求める投稿