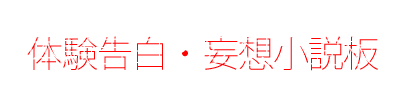
- 投稿される方は、無償且つ時間を掛けて文章を書き投稿されています。閲覧される方は、出来る限りお礼や感想(批判は×)を付けて頂けるようお願い致します。小説・体験投稿者のモチベーションを下げる返信等は削除、連投される場合はアクセス制限対応します。
- トピックの選択(特に、男性or女性、現実と妄想の区分けには御注意下さい)
- 投稿・返信は固定ハンドルネームでお願いします。
低い唸り声を上げて電車が動きだすと、慣性の法則に従った乗客たちが揺れた。朝7時31分《桜が丘記念公園》発の西九条メトロだ。一周16キロメートルある路線をぐるぐると回る。車掌だけが乗車する最先端の自動運転なので、開通して半年経った今でも撮り鉄や乗り鉄が集まってくる。
おれはホームと反対側のドア――つまり対向車輌とすれ違う出入り口付近に立って理性を鼓舞していた。目の前を四人の女子C学生に立ち塞がれているのだ。甘酸っぱい香りと成育し始めた身体が刺激的すぎて、心を無にしない限り色欲に克てそうになかった。
……電車が次の駅に停まって乗降が始まった。彼女たちのセーラー服は聖光女学院を示している。ということは終点ひとつ前でしか降りないのだ。終点まで乗車するおれはあと二十分弱、このソドム的な誘惑に耐えなければならなかった。
(やめれ)
連結部分の広いスペースにどんどん乗客が乗り込んでくる。窮地を脱しようにも人波に邪魔されて叶うことがなかった。それどころか満員電車の悪戯で、C学生のひとりの背中に股間を押しつける恰好になってしまった。当然、愚息はフル勃起状態。彼女がリュックを背負っていればごまかせたけれど、あいにく手提げていた。
彼女が友達に向かって何やら囁く。その中の一人がチラッとおれを一瞥したので、どんな会話が交わされているか想像がついた。このままでは不可抗力なのに通報されてしまう。
(おれのせいじゃないから。痴漢する気なんてゼロだし……アレが硬くなったのは男の生理現象というやつで)
心の中で弁明しても伝わるわけがない。
背中にフル勃起を押しつけられている三つ編みの美少女が振り向いた。
「さっきから背中にぶつかってます」
「ごめん……わざとじゃないんだ。混んでるから身動きが取れなくて」
「混んでると勃起するとか意味わかんないです」
「そんなはっきり言わないで。痴漢と間違われる」
おれは人差し指を鼻先に立てた。ありがたいことに他の乗客はスマホ操作に夢中で気づいていなかった。
「離れないと叫びますよ」
「まじでやめれ。痴漢の冤罪で逮捕とか人生詰む」
友達がスマホアプリを見せてくる。痴漢対策用のSOSアプリだ。叫べない時に、代わりに窮地を喧伝してくれる被害者の味方。
だがこの状況じゃ被害者はおれだ。意図していない密着状態で痴漢容疑をかけられ、窮鼠に追い込まれている。
三つ編みの美少女が髪を背中に流した。
「じゃあ叫ばない代わりに懲らしめてあげます。その雑魚ち○こ、変態属性ですよね」
「雑魚ち○ことか変態属性とかC学生が使う言葉かよ」
「C学生に興奮しておいてなに言ってるんですか」
「う……」
おれはうめいた。女運に恵まれない星のもとに生まれて三十余年。満たされない日々を送るおれの欲動はいつしかレールを外れていた。同世代や年上ではなく、子供以上大人未満の身体にときめくようになったのだ。女の子の誘い方も下着の脱がせ方も知らないので、経験値のある女性には臆病になってしまう。精神年齢が同じレベルの女の子を理想とするのはある意味当然と言えた。
三つ編みの美少女が要求してきた。
「その勃起見せてみて」
見せろと言われて「はいわかりました」と応じる男がいるかよ……とノーマル世界の人々は一笑に付すかもしれない。が、性癖が歪んだ世界にはちゃんと存在する。
おれみたいな人間だ。ふにゃちんやフル勃起を見て女の子が照れたり驚いたりするリアクションに興奮するのだ。しかも今、露出を求めてきたのは彼女たちのほうだからおれに非はない。
「見せられるわけないだろ」
一応拒んでみる。
「周りにバレないようにするから」
四人が取り囲んで防壁を維持した。ちなみに美少女以外の三人は、ローポニーテールの垢抜けない感じの子、ショートヘアのあどけない顔立ちの子、そしてSOSアプリをちらつかせる大人びた子だ。学年がバラバラのようにも思えるが、クラスメイトでも不自然じゃない。
「露出した途端に叫ぶんだろ。それこそ現行犯で釈明の余地がない」
「叫ばない。ただ懲らしめるだけ」
「どうやって」
「さあ」
とぼけてみせる瞳はすでに小悪魔的な光を宿していた。女子C学生に主導権を握られている惨めさがエム魂をくすぐる。
逡巡した末、おれは欲動の下僕となってジッパーに手を掛けた。あんまり常識人ぶりが過ぎると、場がしらけて本気で叫ばれかねない雰囲気だったのだ。
モゾモゾとスラックスの中に手を突っ込んでトランクスを下げ、がちがちに勃起した肉棒を取り出す。瞬間、夢が叶った感動で立ちくらみがした。
四人が半秒ほど絶句する。生意気な態度をしながらも、生ち○ぽの衝撃に怯むのはまだ性が好奇心の対象だけで経験を伴っていない証だ。
三つ編みの美少女がクールな微笑みを浮かべ、垢抜けない子がフリーズし、童顔の子が照れ、アプリの子がより好奇心を強めた。
「すごい上向いてる」
「喜んでるんだよ、きっと。真衣菜の身体にくっつけてもらったから」
「まじ変態……」
「頬っぺたが熱くなってきた」
それぞれの言葉に返答するかのように肉棒がぴくつく。
おれは箍(たが)の外れた欲動に従うまま肉棒を見せつけた。こういうハーレム状態で勃起鑑賞されることがどれほどの憧れだったか。
四人が凝視してくる。爽快感と羞恥心とがない交ぜになり快感に転化した。
「どこが亀頭でどこが裏筋?」
三つ編みの美少女が尋ねてきた。
「この先っぽの亀みたいな部分が亀頭で、裏側のここが裏筋。で、ここがカリ首って言うんだけど……保健体育の授業で習わなかった?」
「教科書だと難しく書いててよくわかんない」
それもそうか。俗語で解説しているはずがない。
「包茎はどういうの?」
アプリの子が尋ねるので、おれは包皮をめくり上げて亀頭を覆い隠した。
「手を放すとほら、こうやってムケちんに戻るんだ。でも世の中には大人になっても皮被りのままで悩んでる人もいるから馬鹿にしちゃだめだぞ」
生ち○ぽを教材に、女子C学生に構造を教えられるなんて露出願望冥利に尽きる。
ひとしきり説明が終わると、三つ編みの美少女が好奇心に促されるように人差し指で亀頭をつついてきた。
「真衣菜、恐くないの?」
「全然。すっごい硬いよ」
すぐに指が離れたが、幼く繊細な感触は微かに心地よかった。
「みんなも触ってみれば?」
という真衣菜ちゃんの誘いにまず乗ったのはアプリの子・莉子ちゃんだった。
真衣菜ちゃんより長い時間、しかも覚えたての裏筋ばかりをつついてくるので、フル勃起が狂喜して硬度を増してしまった。将来、抜群のハンドテクを会得する素質を感じた。
そんな莉子ちゃんに手を取られて無理やりち○ぽタッチさせられたのは童顔の子・芽衣ちゃんだ。ただ恥ずかしがりやなので触れるのも一瞬で、触感が肉棒に伝わった時にはもう指先を離し、沸騰しそうな顔で俯いていた。
最後の葉月ちゃんだけは頑として拒絶した。フル勃起を興味津々そうに見つめていたのに拒否るということは、彼女なりの真意があるのだろう。偏見かもしれないけど、ヲタクそうな印象からして、初体験は推しのアニメキャラに捧げると決めているような。
「オ○ニーしてみて」
真衣菜ちゃんが小悪魔レベルを上げる。
これじゃ懲罰っていうかご褒美だ。
普段の速度でシコるとすぐ逝ってしまいそうなので、おれは四人の視線を脳裏に焼きつけるようにゆっくりとしごいた。
真衣菜ちゃんと莉子ちゃんがクスクスと含み笑いを浮かべ、芽衣ちゃんが恥ずかし照れながら息を呑み、葉月ちゃんが無表情に鑑賞する。それぞれのリアクションに大満足だ。
(まじ最高……)
電車の乗降が始まれば四人がちゃんとガードしてくれる。おれは生涯に一度きりの幸運を満喫するようにセンズリを続けた。
「亀頭が真っ赤になってる」と莉子ちゃん。
「気持ちよすぎて……みんなでもっといっぱい見てて」
おれは超スローテンポでしごいては、ノーマルスピードにギアチェンジする行為を繰り返した。始めはささやかだった射精欲が蓄積し、時折小休止しないと暴発しそうなムズ痒さに成長している。興奮で全身が汗ばんでいた。
「先っぽからなんか垂れてる」
真衣菜ちゃんが気づいた。
「我慢汁。射精の準備部隊みたいなやつで興奮すると滲んでくるんだ」
おれは指先で我慢汁をすくって糸を引かせ、四人の注目をさらに集めた。
「おちん○んのよだれ的な?」
「そう」
やがて電車が終点二つ前の駅を出発した。彼女たちが降りる《聖光学園都市》まで残り三分。暢気(のんき)にしこしこシーンだけ楽しんでいると、肝心な射精を鑑賞されないで終わるという蛇の生殺し状態を迎える。
おれは我慢のストッパーを外して高速でしごいた。
「もうすぐ精子出るからね……出すとこ見ててくれる?」
「うん」
発汗がいっそう強まり、利き手の筋肉が強張りはじめた時、亀頭のムズ痒さが膨張し極大値に達した。
途端、尿道口から壊れたダムみたいにぽたぽたと精液がこぼれ、やがて決壊して弾道鋭く噴出した。どぴゅっ……どぴゅっ、どぴゅっと、矢継ぎ早に真衣菜ちゃんのセーラー服に飛び散る。我ながらとんでもない量だった。女子C学生を生おかずにできる感動――いや、恥ずかしい射精シーンを見てもらえる満足感が余計に絶頂を煽り、震えるほどの快感が人生最長時間続いた。
四人は「わ」とか「きゃっ」とか小さな悲鳴を上げただけで唖然としている。反射的に後ずさったけれど、狂喜したスペルマは軽々と飛距離を維持した。
金玉が空っぽになった感覚になって射精を終えた時、利き手は粘液まみれだった。
「……き、気持ちよかった」
「精子ってこんな飛ぶの?」
「真衣菜の服にめっちゃかかった」
「…………」
「びっくりすぎて言葉が出ない。ていうか超恥ずかしい」
欲動を充足させてもらった肉棒は賢者タイムに入るのも忘れ、余韻に浸るかのようにぴくんぴくん脈打っている。
「ごめん。セーラー服にいっぱいかけちゃった。シミになっちゃうかも」
「大丈夫。学校に行ったらジャージに着替えるから」
それまで漂白剤くさいおれの精液まみれで登校するのか。……いや、さすがにポケットティッシュでもう拭きはじめている。
おれも雑魚ち○こを拭い、ズボンの中に収納した。当面の間、この奇跡的な経験をおかずに人生を頑張れる。
《聖光学園都市》に到着し四人が電車を降りていった。手を振ったら振り返してくれたのは、お仕置き――ご褒美が終わった証かもしれない。
(また会えるかな)
再会した時にもセンズリ鑑賞してくれるとは限らないが、そんな希望を持ってしまうのも正直なところだ。
終点に到着して改札口を通った時、おれは興奮で理性を失っていた自分を呪った。
(真衣菜ちゃん以外にもぶっかければよかった。……なんで二度とない女子C学生のセンズリ鑑賞をスマホで撮影してなかったんだよ――!)
妄想寄稿『間もなく電車で発射致します』END
おれはホームと反対側のドア――つまり対向車輌とすれ違う出入り口付近に立って理性を鼓舞していた。目の前を四人の女子C学生に立ち塞がれているのだ。甘酸っぱい香りと成育し始めた身体が刺激的すぎて、心を無にしない限り色欲に克てそうになかった。
……電車が次の駅に停まって乗降が始まった。彼女たちのセーラー服は聖光女学院を示している。ということは終点ひとつ前でしか降りないのだ。終点まで乗車するおれはあと二十分弱、このソドム的な誘惑に耐えなければならなかった。
(やめれ)
連結部分の広いスペースにどんどん乗客が乗り込んでくる。窮地を脱しようにも人波に邪魔されて叶うことがなかった。それどころか満員電車の悪戯で、C学生のひとりの背中に股間を押しつける恰好になってしまった。当然、愚息はフル勃起状態。彼女がリュックを背負っていればごまかせたけれど、あいにく手提げていた。
彼女が友達に向かって何やら囁く。その中の一人がチラッとおれを一瞥したので、どんな会話が交わされているか想像がついた。このままでは不可抗力なのに通報されてしまう。
(おれのせいじゃないから。痴漢する気なんてゼロだし……アレが硬くなったのは男の生理現象というやつで)
心の中で弁明しても伝わるわけがない。
背中にフル勃起を押しつけられている三つ編みの美少女が振り向いた。
「さっきから背中にぶつかってます」
「ごめん……わざとじゃないんだ。混んでるから身動きが取れなくて」
「混んでると勃起するとか意味わかんないです」
「そんなはっきり言わないで。痴漢と間違われる」
おれは人差し指を鼻先に立てた。ありがたいことに他の乗客はスマホ操作に夢中で気づいていなかった。
「離れないと叫びますよ」
「まじでやめれ。痴漢の冤罪で逮捕とか人生詰む」
友達がスマホアプリを見せてくる。痴漢対策用のSOSアプリだ。叫べない時に、代わりに窮地を喧伝してくれる被害者の味方。
だがこの状況じゃ被害者はおれだ。意図していない密着状態で痴漢容疑をかけられ、窮鼠に追い込まれている。
三つ編みの美少女が髪を背中に流した。
「じゃあ叫ばない代わりに懲らしめてあげます。その雑魚ち○こ、変態属性ですよね」
「雑魚ち○ことか変態属性とかC学生が使う言葉かよ」
「C学生に興奮しておいてなに言ってるんですか」
「う……」
おれはうめいた。女運に恵まれない星のもとに生まれて三十余年。満たされない日々を送るおれの欲動はいつしかレールを外れていた。同世代や年上ではなく、子供以上大人未満の身体にときめくようになったのだ。女の子の誘い方も下着の脱がせ方も知らないので、経験値のある女性には臆病になってしまう。精神年齢が同じレベルの女の子を理想とするのはある意味当然と言えた。
三つ編みの美少女が要求してきた。
「その勃起見せてみて」
見せろと言われて「はいわかりました」と応じる男がいるかよ……とノーマル世界の人々は一笑に付すかもしれない。が、性癖が歪んだ世界にはちゃんと存在する。
おれみたいな人間だ。ふにゃちんやフル勃起を見て女の子が照れたり驚いたりするリアクションに興奮するのだ。しかも今、露出を求めてきたのは彼女たちのほうだからおれに非はない。
「見せられるわけないだろ」
一応拒んでみる。
「周りにバレないようにするから」
四人が取り囲んで防壁を維持した。ちなみに美少女以外の三人は、ローポニーテールの垢抜けない感じの子、ショートヘアのあどけない顔立ちの子、そしてSOSアプリをちらつかせる大人びた子だ。学年がバラバラのようにも思えるが、クラスメイトでも不自然じゃない。
「露出した途端に叫ぶんだろ。それこそ現行犯で釈明の余地がない」
「叫ばない。ただ懲らしめるだけ」
「どうやって」
「さあ」
とぼけてみせる瞳はすでに小悪魔的な光を宿していた。女子C学生に主導権を握られている惨めさがエム魂をくすぐる。
逡巡した末、おれは欲動の下僕となってジッパーに手を掛けた。あんまり常識人ぶりが過ぎると、場がしらけて本気で叫ばれかねない雰囲気だったのだ。
モゾモゾとスラックスの中に手を突っ込んでトランクスを下げ、がちがちに勃起した肉棒を取り出す。瞬間、夢が叶った感動で立ちくらみがした。
四人が半秒ほど絶句する。生意気な態度をしながらも、生ち○ぽの衝撃に怯むのはまだ性が好奇心の対象だけで経験を伴っていない証だ。
三つ編みの美少女がクールな微笑みを浮かべ、垢抜けない子がフリーズし、童顔の子が照れ、アプリの子がより好奇心を強めた。
「すごい上向いてる」
「喜んでるんだよ、きっと。真衣菜の身体にくっつけてもらったから」
「まじ変態……」
「頬っぺたが熱くなってきた」
それぞれの言葉に返答するかのように肉棒がぴくつく。
おれは箍(たが)の外れた欲動に従うまま肉棒を見せつけた。こういうハーレム状態で勃起鑑賞されることがどれほどの憧れだったか。
四人が凝視してくる。爽快感と羞恥心とがない交ぜになり快感に転化した。
「どこが亀頭でどこが裏筋?」
三つ編みの美少女が尋ねてきた。
「この先っぽの亀みたいな部分が亀頭で、裏側のここが裏筋。で、ここがカリ首って言うんだけど……保健体育の授業で習わなかった?」
「教科書だと難しく書いててよくわかんない」
それもそうか。俗語で解説しているはずがない。
「包茎はどういうの?」
アプリの子が尋ねるので、おれは包皮をめくり上げて亀頭を覆い隠した。
「手を放すとほら、こうやってムケちんに戻るんだ。でも世の中には大人になっても皮被りのままで悩んでる人もいるから馬鹿にしちゃだめだぞ」
生ち○ぽを教材に、女子C学生に構造を教えられるなんて露出願望冥利に尽きる。
ひとしきり説明が終わると、三つ編みの美少女が好奇心に促されるように人差し指で亀頭をつついてきた。
「真衣菜、恐くないの?」
「全然。すっごい硬いよ」
すぐに指が離れたが、幼く繊細な感触は微かに心地よかった。
「みんなも触ってみれば?」
という真衣菜ちゃんの誘いにまず乗ったのはアプリの子・莉子ちゃんだった。
真衣菜ちゃんより長い時間、しかも覚えたての裏筋ばかりをつついてくるので、フル勃起が狂喜して硬度を増してしまった。将来、抜群のハンドテクを会得する素質を感じた。
そんな莉子ちゃんに手を取られて無理やりち○ぽタッチさせられたのは童顔の子・芽衣ちゃんだ。ただ恥ずかしがりやなので触れるのも一瞬で、触感が肉棒に伝わった時にはもう指先を離し、沸騰しそうな顔で俯いていた。
最後の葉月ちゃんだけは頑として拒絶した。フル勃起を興味津々そうに見つめていたのに拒否るということは、彼女なりの真意があるのだろう。偏見かもしれないけど、ヲタクそうな印象からして、初体験は推しのアニメキャラに捧げると決めているような。
「オ○ニーしてみて」
真衣菜ちゃんが小悪魔レベルを上げる。
これじゃ懲罰っていうかご褒美だ。
普段の速度でシコるとすぐ逝ってしまいそうなので、おれは四人の視線を脳裏に焼きつけるようにゆっくりとしごいた。
真衣菜ちゃんと莉子ちゃんがクスクスと含み笑いを浮かべ、芽衣ちゃんが恥ずかし照れながら息を呑み、葉月ちゃんが無表情に鑑賞する。それぞれのリアクションに大満足だ。
(まじ最高……)
電車の乗降が始まれば四人がちゃんとガードしてくれる。おれは生涯に一度きりの幸運を満喫するようにセンズリを続けた。
「亀頭が真っ赤になってる」と莉子ちゃん。
「気持ちよすぎて……みんなでもっといっぱい見てて」
おれは超スローテンポでしごいては、ノーマルスピードにギアチェンジする行為を繰り返した。始めはささやかだった射精欲が蓄積し、時折小休止しないと暴発しそうなムズ痒さに成長している。興奮で全身が汗ばんでいた。
「先っぽからなんか垂れてる」
真衣菜ちゃんが気づいた。
「我慢汁。射精の準備部隊みたいなやつで興奮すると滲んでくるんだ」
おれは指先で我慢汁をすくって糸を引かせ、四人の注目をさらに集めた。
「おちん○んのよだれ的な?」
「そう」
やがて電車が終点二つ前の駅を出発した。彼女たちが降りる《聖光学園都市》まで残り三分。暢気(のんき)にしこしこシーンだけ楽しんでいると、肝心な射精を鑑賞されないで終わるという蛇の生殺し状態を迎える。
おれは我慢のストッパーを外して高速でしごいた。
「もうすぐ精子出るからね……出すとこ見ててくれる?」
「うん」
発汗がいっそう強まり、利き手の筋肉が強張りはじめた時、亀頭のムズ痒さが膨張し極大値に達した。
途端、尿道口から壊れたダムみたいにぽたぽたと精液がこぼれ、やがて決壊して弾道鋭く噴出した。どぴゅっ……どぴゅっ、どぴゅっと、矢継ぎ早に真衣菜ちゃんのセーラー服に飛び散る。我ながらとんでもない量だった。女子C学生を生おかずにできる感動――いや、恥ずかしい射精シーンを見てもらえる満足感が余計に絶頂を煽り、震えるほどの快感が人生最長時間続いた。
四人は「わ」とか「きゃっ」とか小さな悲鳴を上げただけで唖然としている。反射的に後ずさったけれど、狂喜したスペルマは軽々と飛距離を維持した。
金玉が空っぽになった感覚になって射精を終えた時、利き手は粘液まみれだった。
「……き、気持ちよかった」
「精子ってこんな飛ぶの?」
「真衣菜の服にめっちゃかかった」
「…………」
「びっくりすぎて言葉が出ない。ていうか超恥ずかしい」
欲動を充足させてもらった肉棒は賢者タイムに入るのも忘れ、余韻に浸るかのようにぴくんぴくん脈打っている。
「ごめん。セーラー服にいっぱいかけちゃった。シミになっちゃうかも」
「大丈夫。学校に行ったらジャージに着替えるから」
それまで漂白剤くさいおれの精液まみれで登校するのか。……いや、さすがにポケットティッシュでもう拭きはじめている。
おれも雑魚ち○こを拭い、ズボンの中に収納した。当面の間、この奇跡的な経験をおかずに人生を頑張れる。
《聖光学園都市》に到着し四人が電車を降りていった。手を振ったら振り返してくれたのは、お仕置き――ご褒美が終わった証かもしれない。
(また会えるかな)
再会した時にもセンズリ鑑賞してくれるとは限らないが、そんな希望を持ってしまうのも正直なところだ。
終点に到着して改札口を通った時、おれは興奮で理性を失っていた自分を呪った。
(真衣菜ちゃん以外にもぶっかければよかった。……なんで二度とない女子C学生のセンズリ鑑賞をスマホで撮影してなかったんだよ――!)
妄想寄稿『間もなく電車で発射致します』END
| ▼ | 妄想寄稿『間もなく電車で発射致します』 Angel Heart 25/1/31(金) 8:15 | ≪ |
| Extra Episode『湯煙妄想紀行』 Angel Heart 25/1/31(金) 8:34 |
| Re:Extra Episode『湯煙妄想紀行』 純西別森木 25/1/31(金) 9:12 |
| Re:Extra Episode『湯煙妄想紀行』 Mr.774 25/2/6(木) 19:32 |
| Re:Extra Episode 純西別森木 25/2/6(木) 19:43 |
| Re:Extra Episode Angel Heart 25/2/7(金) 8:26 |
| Re:Extra Episode『湯煙妄想紀行』 Angel Heart 25/2/7(金) 7:52 |
| Re:Extra Episode『湯煙妄想紀行』 ろくべえ 25/2/8(土) 9:41 |
| Re:Extra Episode 純西別森木 25/2/8(土) 10:42 |
| Re:妄想寄稿『間もなく電車で発射致します』 純西別森木 25/1/31(金) 9:10 |
| Extra Episode『ユーノーの祝福』 Angel Heart 25/1/31(金) 17:38 |
| Re:Extra Episode『ユーノーの祝福』 純西別森木 25/1/31(金) 18:04 |
| Extra Episode『ユーノーの祝福 半分この帰り道』 Angel Heart 25/2/14(金) 18:26 |
| Re:Extra Episode『ユーノーの祝福 半分この帰り道』 純西別森木 25/2/14(金) 19:41 |
| Extra Episode『うらすじ太郎』 Angel Heart 25/2/3(月) 18:52 |
| Re:Extra Episode『うらすじ太郎』 純西別森木 25/2/3(月) 19:14 |
| Re:Extra Episode『うらすじ太郎』 LEVEL E 25/2/4(火) 12:16 |
| Re:Extra Episode『うらすじ太郎』 純西別森木 25/2/4(火) 12:27 |
| Re:Extra Episode『うらすじ太郎』 Angel Heart 25/2/4(火) 13:39 |
235,824
禁止事項
- 誹謗・中傷・乱暴な言葉遣い
- 無神経なage行為・過度な連続投稿
- 対象者の名誉を傷つけるスキャンダル等
- 個人が特定できるような地域情報
- 18歳未満を対象とした(成人が未成年を相手にする犯罪に該当する)告白投稿
- 出会いを求める投稿