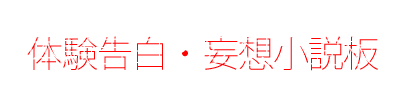
- 投稿される方は、無償且つ時間を掛けて文章を書き投稿されています。閲覧される方は、出来る限りお礼や感想(批判は×)を付けて頂けるようお願い致します。小説・体験投稿者のモチベーションを下げる返信等は削除、連投される場合はアクセス制限対応します。
- トピックの選択(特に、男性or女性、現実と妄想の区分けには御注意下さい)
- 投稿・返信は固定ハンドルネームでお願いします。
「私からで良いでしょう?」
妻の特権だとばかりに凛子に目配せする恭子。年下の従妹はどうぞとばかりに肩をすくめ、余裕を見せつけます。すると恭子はすぐに私の方に向き直り、
「私以外の女の前で勃起させるなんて悪いオチンチンね…」
上目づかいで私を睨みながら、白肌のスライム乳の深い谷間を開帳しました。まるで別の生き物のようにプルルンと揺れる乳房を両手で支えた妻は、双子の肉果実の狭間にイチモツを導くと、
「んっ…すっごい硬い…。もう先走りが出ちゃって…んれろおお…」
長い舌肉を嫌らしく伸ばし、紅色の肉塊から唾液を滴らせました。泡立った液体は銀色の糸と化して舌先から零れ落ち、すでに鈴割れから青臭い汁を漏らしていた亀頭を覆い尽します。
「ううっ…んっ…」
竿の付け根が痛みを覚えるぐらいギンギンに漲っていた私は、唾液が零れただけで情けない呻きを上げてしまいました。肉竿を左右から挟み込む白き肉果実の柔らかさは、ゆりかごのような安心感で私を癒すと同時に、汗ばんだ白肌が熱く猛った剛棒に吸い付きます。
「恭子…もっと…」
囁くように声をかけた私に、恭子は魔性の笑みを披露しました。目力の強い瞳が微妙に潤み、ショートカットから覗く耳たぶは真冬に外をうろついたときのように真っ赤に染まっています。それが妻自身の興奮を表すことを知っていた私は、心臓が早鐘を打つのを止められませんでした。
「たっぷり焦らしてあげる。だらしない顔したお仕置きよ」
恭子は妖しく囁きを返すと、左右の手に力を込めて谷間に差し挟んだ肉竿をしごき始めました。唾液と先走り汁、そして恭子の汗が潤滑油となり、滑らかな肌の感触を強調します。毎夜の如く挟んでもらっている身でありながら、私はこの刺激に慣れるどころか、日に日に貪欲になっていました。
スイカほどもありそうな巨大乳房を前にしては、私の愚息など子供同然です。妻曰くサイズ的には立派なイチモツだそうですが、熟女の乳肉はそれさえもすっぽり包んでしまうボリュームを誇っています。
さらにいえば、私とのまぐわいによって恭子は熟達したパイズリ技術を習得していました。
「んっ…んっ…。オチンチン、ビクビクしちゃってるね。気持ち良いんでしょ?良いよ、何も言わなくて。シン君のオチンチンなら、私全部知ってるから。あ、また跳ねた。さきっちょも膨らんで…んっ…こら、腰動かさないの」
凛子がすぐそばで見守っているにも拘わらず、恭子は2人きりでベッドにいるのと変わらない様子で肉棒を弄んでいます。そんな恭子も身体を重ねるようになったばかりの頃は、いやいやながらパイズリをしていました。
あの頃の初々しさも良いですが、力強い瞳を輝かせる今の彼女の方が何倍も股間を刺激します。
小刻みに上下動をしたかと思えば、なだらかな乳布団がウェーブを描いて竿全体を包み込む予測不可能な攻め。ときおり挟み込む圧力を変えたり、カリ首に近いポイントを集中してしごきあげられた私は、堪らず呼吸を荒らげて背中を仰け反らせました。
すると妻は意地の悪いことに、真っ白なスライム乳房の圧力を弱めたのです。
「だーめ。まだイっちゃ。シン君、こっち見て?」
妻の言う通りに視線を移すと、セクシーな口元の黒子を歪めた恭子がこちらを見上げていました。歯科衛生士だった彼女と最初に会ったとき、私は虫歯を治すために来院した患者でした。
マスク姿の恭子の目力に圧倒され、必死にアプローチして漕ぎつけたデート当日。思えばあのときがマスクをしていない彼女を見た初めての機会です。そのとき発見した口元の黒子の色っぽさが、今日は一段と輝いているようでした。
「おねだり、できるでしょう?いつも私にしてるもんね?」
性癖の暴露を強要する妻に対して、強い態度を示せるほど私は人間ができていません。最近は頓にパイズリで主導権を奪われることが多くなった私は、
「お願い…します。もっと激しく…うぅ…擦ってくださ…ああっ…」
会社の同僚が聞いたら全員が連絡先を消去するであろう情けない声色で、妻にさらなる愛撫を懇願しました。それが終わる直前に、妻はウインクしながら挟み込みを再開します。
「よく言えました。シン君は本当に、私のおっぱいが大好きなのね」
これまで一切凛子を気にしなかった妻の視線がチラッと背後に向くと、そこには猟銃を構えたハンターのような鋭い視線を携えた凛子が腕組みして立っています。
年下の従妹の眼差しを背中に受けたまま、恭子の乳愛撫はダイナミックな動きに転じ、亀頭が膨らむほど焦らされたイチモツの根元から何かが湧き上がっていきました。
スライム乳は柔らかい分、横乳に添えた手の圧力がダイレクトに伝わってきます。極上の柔らかさに熟達したテクニックが味方をしてはもう、私には成す術もありません。
「ああっ…恭子…出るっ…」
それまで仰け反らせていた背中を丸め、乳布団と肉棒の摩擦を強めんと腰を振り始めたそのとき、我慢汁でヌラヌラと光っていた鈴割れから怒涛の勢いで精液が噴き出しました。
尻がベッドから浮き上がるほどの心地良さが全身を駆け巡ると、鈴割れを覗き込んでいた恭子の口元に白く濁った噴水がぶち当たりました。
自慰とは比べ物にならない昂ぶりと多幸感に脳汁が溢れ、長々と息を吐く私を尻目に、妻は噴き上げた白濁汁の処理に追われています。
「はむっ…んんっ…ちゅちゅっ…はあっ…んふうっ…とっても濃いわ。昨日もあんなにだしたのに…んっ…れろお…」
口元や乳房にかかった精液を指で掬い取り、口内へと運ぶ仕草はその辺のアダルトな映像では見られない艶っぽさ。
「恭子…」
と呟く私のイチモツは、出したばかりだというのに再び熱を帯び始めました。恭子は上目遣いの目を細めると、
「んちゅっ…んれろお…んちゅぱあ…」
普段よりもいっそう甲斐甲斐しく、白濁汁で濡れたイチモツに丁寧に舌を走らせました。唾液と精液が混じった液体に包み込まれた舌肉は、スライム乳とは別種の快感をもたらします。
「お姉ちゃん、パイズリ対決でしょ?フェラは反則じゃない?」
恭子の愛撫中一度も口を挟まなかった凛子の鋭い声。しかし恭子は臆することなく、
「んれろお…あら、ごめんなさい。うちではいつも、パイズリのあとこうしてるから…。んちゅっ…。ね、シン君?」
ともすればぶりっ子と言われても仕方がない甘い声で、私に尋ねてきました。凛子へのあてつけに違いないのはわかっていますが、こういった仕草も可愛く見えてしまうのが惚れた弱みというものです。
「ああ、そうだね」
と同意した私の顔が緩み切っていたことは、鏡を見なくても想像に難くありません。
「もういいよ、そういうのは全部私がやるから、お姉ちゃんはどけて」
私たちののろけを見事にスルーした凛子は、恭子のすぐ横で膝を立てると、若さ漲るJカップ爆乳で妻の腕を押しました。すると妻の余裕たっぷりの面差しが陰りを帯びて、
「くっ…」
と奥歯を噛みしめて肉棒を開放します。凛子の乳房の実力を改めて思い出しながらも妻が素直に引き下がったのは、今回のパイズリ対決で従妹を負かしたいという強い思いの表れでした。
「お待たせしました。私はお姉ちゃんみたいに焦らしたりしないから安心してね」
凛子は化粧のおかげでパッチリとした印象の目元を瞬かせると、左右の乳肉を斜め下から抱え上げるようにして深い谷間を開帳しました。
こうして間近で見ると、妻と凛子の乳肉の違いが明白に感じ取れます。ブラのカップ的には1つしか違わないことが判明しましたが、20代の張りと弾力を備えた乳肉は、三十路のスライム乳よりも厚みで勝っているように思えます。
乳首を中心としたビキニ型の白肌と、オーストラリアのビーチで焼いてきた健康的な小麦肌のコントラストが、健康的な魅力に卑猥さのスパイスとして機能しているのです。
妻を貶める気は一切ありませんが、巨乳好きを自負する私としては正当な評価をせざるを得ません。
そんな私の胸の内を読み取ったかのように、凛子は妖しく口元を歪めると、
「お姉ちゃんのおっぱいと、どっちが良い?」
と尋ねながら、卑猥にギラつく肉棒をギュッと谷間に挟み込みます。瞬間、まるで極上の羽毛布団に包まれたような心地良さと、スプリングの利いたベッドに背中を預けたときにも似た解放感がイチモツから迸りました。
「んっっ…!」
こちらをじっと睨む妻の目を気にして、私は必死に呻きを抑えようと試みます。しかし凛子の乳果実の感触は、そんな決意を簡単に粉々にしてしまう心地良さに溢れていました。
指で押したらどこまでも沈んでいきそうなスライム乳の柔らかさとはまるで違う、どこか芯のあるしっかりとした弾力。
張りのある乳肉と乳肉の間に挟まれたオスの象徴は、まだ挟んだだけなのにジンジンと根元から熱くなってしまったのです。
「全然違うでしょ?お姉ちゃんのペラペラでダルンダルンなおっぱいじゃ、この感じは無理…ですよね?」
敬語とタメ口を織り交ぜた独特の口調で問う凛子の瞳には、先ほどの恭子に負けず劣らずの魔性の光が宿っていました。
身長に比例した長い舌が、心臓をキュッと締め付けるほどの色香を湛えています。凛子は私がごくりと生唾を呑み込んだのを確認すると、妖しげな笑みを浮かべて横乳をグイグイと押し始めました。
「うっ…くぅう…」
私は恥ずかしながら、妻の若い頃の乳肉を思い出してしまいました。弾力のある乳房は上下にこき上げるまでもなく肉棒を跳ね返し、極上の感触でマッサージを繰り出します。
妻も出産する前はこれに近い弾力を誇っていましたが、正直なところ過去の妻よりも凛子の方が勝っているといわざるを得ません。
私の反応を凛子の横で窺っている妻の顔に、焦りと悔しさが滲んでいきます。皮肉なことに、パイズリに圧倒的な自信を持っている妻のそんな表情がマラ棒をさらに熱くするのでした。
「お兄さんのオチンチン、すっごく硬いですね。あんっ…私まで熱くなってきちゃった…んっ…はあっ…」
凛子が首を振ってオレンジブラウンのセミロングを払うと、汗が浮かんだ首筋が露になります。極上ボディのうら若き乙女が自分の肉棒を挟み込み、昂っているのを目の前にして平常な気持ちを保てというのは無理な話です。
すでにギンギンに漲っていた私のオス肉が、海綿体の膨張を最大まで強めていきます。それを見計らっていたかのように、凛子はくびれた腰を上下に動かして、Jカップ爆乳全体で私の肉棒を悦楽の布団で包み込みました。
「出しちゃっていいんですよ?お兄さんの濃いザーメン、私に飲ませて?」
上目遣いの凛子の瞳が潤み、物欲しげにパクパクと口を動かして私を挑発します。学生時代は奥手で、大学生になってもまともな恋愛ができないと恭子に相談していた初心な少女は、艶めかしい表情で男を惑わす女になっていました。
「うっ…ああっ!もう…だめだ…出るっ…」
心臓が早鐘を打ち始めて数秒にも満たないうちに、海綿体が爆発しそうな勢いでオスの昂ぶりが襲来しました。張りの強い乳房に揉まれた心地良さは、我慢の文字を私の辞書から取り去ってしまったようです。
どぴゅっと舞い上がる白濁の液体は凛子の鼻先をかすめ、小麦色の乳肉や顔面に降り注ぎました。
「あんっ…すっごーい。んちゅっ…れろおお…。2回目なのにたっぷり出ましたね。そんなに私のパイズリ、気持ち良かったですか?」
凛子は顔面や乳房を汚したオスの絶頂汁に構うことなく、愚息の亀頭にまとわりついた白濁のヴェールを舌で絡め取りました。舌先が鈴口を突きまわすと、
「うぅ…凛子ちゃん…そこは…」
腰が浮き上がりそうな快感に呻いてしまいます。これは口淫の方も相当できるに違いないとふしだらな想像が私の脳裏を過ったそのとき、妻の鋭い声が耳に届きました。
「そこまでよ。凛子、シン君から離れなさい」
「んちゅっ…。お姉ちゃんだってオチンチン舐めてたのに、ずるいですよねえ?」
凛子は文句を垂れながらも素直に身を引き、Jカップ爆乳の圧迫を解きました。長い間背負っていた重い荷物を下ろしたときのような開放感が物語るのは、凛子の乳房の弾力強さです。
ホッと息を吐く私でしたが、すぐに恭子のスライム乳が半勃ちにまで萎んでいた男根を包み込みました。
「シン君、まだまだ出るでしょ?だって昨日もいっぱい射精したもんね?」
煽るような言葉を吐く恭子でしたが、その声が若干震えていることに私は気づきました。これは夫婦だからこそわかる声色の変化です。そして私は、妻を不安にさせている原因についても心当たりがありました。
2回目の射精で放った私の精液が、いつも恭子のパイズリで出している量よりも遙かに多かったからです。私は妻の不安を少しでも和らげるために、
「ああ。頼むよ、恭子」
と言いながら彼女の頭を優しく撫でました。普段であれば目力の強い瞳で私を睨みつけながら、
「挟んでもらってる分際で生意気なことしないでくれる?」
と悪態をつくのですが、今日に限っては素直に頷いて、
「ありがとう。私、頑張るから…」
儚くも色気を携えた笑みを浮かべたのです。ひたむきな妻に奉仕させていることへの背徳感が、萎れかけの肉棒を見る見るうちに漲らせました。
私の昂ぶりを肌で感じ取った妻は、スライム乳をパン生地のように捏ねまわして艶めかしいマッサージを開始します。
「んっ…ふうっ…んぐっ…はあっ…」
妻は熱い吐息が亀頭を何度も撫でるほど息を荒らげながらも、私から目を離すことはありません。
すでに2度射精していることもあり、これまでよりも射精欲が沸き上がりにくくなっていることを承知のうえで、必死に奉仕をする恭子。
女神のような美貌と、カウパーや精液で汚された乳房の淫猥な光のコントラストは、1枚の写真に切り取りたいほど神々しく、鉄のように硬くなった愚息を翻弄します。
乳房の質で勝負していた凛子のそれとは違い、力の入れ加減や方向、柔肌の滑らせ方まで洗練された乳奉仕。
心臓がバクバクと小刻みなビートを刻みだし、玉袋がキュッとせり上がります。
しかし私の口元が歪むのを見るや否や、恭子はまたも焦らし始めるのです。
「だめ。まだだよ。凛子のときよりいっぱい出してくれないと…んっ…いやだから…」
そう言いながら妻は舌肉を伸ばすと、亀頭の先に触れる直前でチロチロと動かしました。パイズリ対決で舌奉仕をするのかいかがなものかと声を上げたそうにする凛子ですが、恭子の舌肉はまさにギリギリのラインで踏みとどまっています。
あの柔らかい肉塊がどれほどの快楽をもたらすのか知っている私は、無意識のうちに腰を動かしてしまいました。それも見事に見通していた恭子は、舌肉をするっと口内に戻すと、
「変態。もっと腰振らないと、ペロペロしてあげないんだから」
口の端を吊り上げながらスライム乳を肉棒にギュッと押し付けてきます。三十路を超えてもなお滑らかな触り心地をキープしている柔肌にギュッと包まれた私は、
「はあっ…はあっ…」
後で思い返しても赤面してしまう必死さで腰を動かしてしまうのでした。これではまさに、私を手玉に取ることに慣れた恭子の思う壺です。
恭子は私の腰振りとは正反対の動きで乳房をこき上げることで、通常のパイズリの2倍近い摩擦を男根に与えることに成功していました。
その快楽たるや、ジェットコースターも顔負けのスリリングな体験です。気持ち良すぎて怖いのに、絶対に途中下車することが許されていない悦楽特急。
「おっ…んぐっ…ああ゛っ…」
私自身は覚えていないのですが、妻によるとこんなにも情けない喘ぎを上げてしまっていたようです。ただし、全ての感覚が肉棒に集結したようなオーガズム体験だけは、いつでも思い出せるほど記憶に残っています。
鼻と口から同時に息を吐き、唾液を飛ばしてしまうほどオスの快楽に酔った私の股間から、噴水も顔負けの真っ白なシャワーが噴き上げました。
妻の特権だとばかりに凛子に目配せする恭子。年下の従妹はどうぞとばかりに肩をすくめ、余裕を見せつけます。すると恭子はすぐに私の方に向き直り、
「私以外の女の前で勃起させるなんて悪いオチンチンね…」
上目づかいで私を睨みながら、白肌のスライム乳の深い谷間を開帳しました。まるで別の生き物のようにプルルンと揺れる乳房を両手で支えた妻は、双子の肉果実の狭間にイチモツを導くと、
「んっ…すっごい硬い…。もう先走りが出ちゃって…んれろおお…」
長い舌肉を嫌らしく伸ばし、紅色の肉塊から唾液を滴らせました。泡立った液体は銀色の糸と化して舌先から零れ落ち、すでに鈴割れから青臭い汁を漏らしていた亀頭を覆い尽します。
「ううっ…んっ…」
竿の付け根が痛みを覚えるぐらいギンギンに漲っていた私は、唾液が零れただけで情けない呻きを上げてしまいました。肉竿を左右から挟み込む白き肉果実の柔らかさは、ゆりかごのような安心感で私を癒すと同時に、汗ばんだ白肌が熱く猛った剛棒に吸い付きます。
「恭子…もっと…」
囁くように声をかけた私に、恭子は魔性の笑みを披露しました。目力の強い瞳が微妙に潤み、ショートカットから覗く耳たぶは真冬に外をうろついたときのように真っ赤に染まっています。それが妻自身の興奮を表すことを知っていた私は、心臓が早鐘を打つのを止められませんでした。
「たっぷり焦らしてあげる。だらしない顔したお仕置きよ」
恭子は妖しく囁きを返すと、左右の手に力を込めて谷間に差し挟んだ肉竿をしごき始めました。唾液と先走り汁、そして恭子の汗が潤滑油となり、滑らかな肌の感触を強調します。毎夜の如く挟んでもらっている身でありながら、私はこの刺激に慣れるどころか、日に日に貪欲になっていました。
スイカほどもありそうな巨大乳房を前にしては、私の愚息など子供同然です。妻曰くサイズ的には立派なイチモツだそうですが、熟女の乳肉はそれさえもすっぽり包んでしまうボリュームを誇っています。
さらにいえば、私とのまぐわいによって恭子は熟達したパイズリ技術を習得していました。
「んっ…んっ…。オチンチン、ビクビクしちゃってるね。気持ち良いんでしょ?良いよ、何も言わなくて。シン君のオチンチンなら、私全部知ってるから。あ、また跳ねた。さきっちょも膨らんで…んっ…こら、腰動かさないの」
凛子がすぐそばで見守っているにも拘わらず、恭子は2人きりでベッドにいるのと変わらない様子で肉棒を弄んでいます。そんな恭子も身体を重ねるようになったばかりの頃は、いやいやながらパイズリをしていました。
あの頃の初々しさも良いですが、力強い瞳を輝かせる今の彼女の方が何倍も股間を刺激します。
小刻みに上下動をしたかと思えば、なだらかな乳布団がウェーブを描いて竿全体を包み込む予測不可能な攻め。ときおり挟み込む圧力を変えたり、カリ首に近いポイントを集中してしごきあげられた私は、堪らず呼吸を荒らげて背中を仰け反らせました。
すると妻は意地の悪いことに、真っ白なスライム乳房の圧力を弱めたのです。
「だーめ。まだイっちゃ。シン君、こっち見て?」
妻の言う通りに視線を移すと、セクシーな口元の黒子を歪めた恭子がこちらを見上げていました。歯科衛生士だった彼女と最初に会ったとき、私は虫歯を治すために来院した患者でした。
マスク姿の恭子の目力に圧倒され、必死にアプローチして漕ぎつけたデート当日。思えばあのときがマスクをしていない彼女を見た初めての機会です。そのとき発見した口元の黒子の色っぽさが、今日は一段と輝いているようでした。
「おねだり、できるでしょう?いつも私にしてるもんね?」
性癖の暴露を強要する妻に対して、強い態度を示せるほど私は人間ができていません。最近は頓にパイズリで主導権を奪われることが多くなった私は、
「お願い…します。もっと激しく…うぅ…擦ってくださ…ああっ…」
会社の同僚が聞いたら全員が連絡先を消去するであろう情けない声色で、妻にさらなる愛撫を懇願しました。それが終わる直前に、妻はウインクしながら挟み込みを再開します。
「よく言えました。シン君は本当に、私のおっぱいが大好きなのね」
これまで一切凛子を気にしなかった妻の視線がチラッと背後に向くと、そこには猟銃を構えたハンターのような鋭い視線を携えた凛子が腕組みして立っています。
年下の従妹の眼差しを背中に受けたまま、恭子の乳愛撫はダイナミックな動きに転じ、亀頭が膨らむほど焦らされたイチモツの根元から何かが湧き上がっていきました。
スライム乳は柔らかい分、横乳に添えた手の圧力がダイレクトに伝わってきます。極上の柔らかさに熟達したテクニックが味方をしてはもう、私には成す術もありません。
「ああっ…恭子…出るっ…」
それまで仰け反らせていた背中を丸め、乳布団と肉棒の摩擦を強めんと腰を振り始めたそのとき、我慢汁でヌラヌラと光っていた鈴割れから怒涛の勢いで精液が噴き出しました。
尻がベッドから浮き上がるほどの心地良さが全身を駆け巡ると、鈴割れを覗き込んでいた恭子の口元に白く濁った噴水がぶち当たりました。
自慰とは比べ物にならない昂ぶりと多幸感に脳汁が溢れ、長々と息を吐く私を尻目に、妻は噴き上げた白濁汁の処理に追われています。
「はむっ…んんっ…ちゅちゅっ…はあっ…んふうっ…とっても濃いわ。昨日もあんなにだしたのに…んっ…れろお…」
口元や乳房にかかった精液を指で掬い取り、口内へと運ぶ仕草はその辺のアダルトな映像では見られない艶っぽさ。
「恭子…」
と呟く私のイチモツは、出したばかりだというのに再び熱を帯び始めました。恭子は上目遣いの目を細めると、
「んちゅっ…んれろお…んちゅぱあ…」
普段よりもいっそう甲斐甲斐しく、白濁汁で濡れたイチモツに丁寧に舌を走らせました。唾液と精液が混じった液体に包み込まれた舌肉は、スライム乳とは別種の快感をもたらします。
「お姉ちゃん、パイズリ対決でしょ?フェラは反則じゃない?」
恭子の愛撫中一度も口を挟まなかった凛子の鋭い声。しかし恭子は臆することなく、
「んれろお…あら、ごめんなさい。うちではいつも、パイズリのあとこうしてるから…。んちゅっ…。ね、シン君?」
ともすればぶりっ子と言われても仕方がない甘い声で、私に尋ねてきました。凛子へのあてつけに違いないのはわかっていますが、こういった仕草も可愛く見えてしまうのが惚れた弱みというものです。
「ああ、そうだね」
と同意した私の顔が緩み切っていたことは、鏡を見なくても想像に難くありません。
「もういいよ、そういうのは全部私がやるから、お姉ちゃんはどけて」
私たちののろけを見事にスルーした凛子は、恭子のすぐ横で膝を立てると、若さ漲るJカップ爆乳で妻の腕を押しました。すると妻の余裕たっぷりの面差しが陰りを帯びて、
「くっ…」
と奥歯を噛みしめて肉棒を開放します。凛子の乳房の実力を改めて思い出しながらも妻が素直に引き下がったのは、今回のパイズリ対決で従妹を負かしたいという強い思いの表れでした。
「お待たせしました。私はお姉ちゃんみたいに焦らしたりしないから安心してね」
凛子は化粧のおかげでパッチリとした印象の目元を瞬かせると、左右の乳肉を斜め下から抱え上げるようにして深い谷間を開帳しました。
こうして間近で見ると、妻と凛子の乳肉の違いが明白に感じ取れます。ブラのカップ的には1つしか違わないことが判明しましたが、20代の張りと弾力を備えた乳肉は、三十路のスライム乳よりも厚みで勝っているように思えます。
乳首を中心としたビキニ型の白肌と、オーストラリアのビーチで焼いてきた健康的な小麦肌のコントラストが、健康的な魅力に卑猥さのスパイスとして機能しているのです。
妻を貶める気は一切ありませんが、巨乳好きを自負する私としては正当な評価をせざるを得ません。
そんな私の胸の内を読み取ったかのように、凛子は妖しく口元を歪めると、
「お姉ちゃんのおっぱいと、どっちが良い?」
と尋ねながら、卑猥にギラつく肉棒をギュッと谷間に挟み込みます。瞬間、まるで極上の羽毛布団に包まれたような心地良さと、スプリングの利いたベッドに背中を預けたときにも似た解放感がイチモツから迸りました。
「んっっ…!」
こちらをじっと睨む妻の目を気にして、私は必死に呻きを抑えようと試みます。しかし凛子の乳果実の感触は、そんな決意を簡単に粉々にしてしまう心地良さに溢れていました。
指で押したらどこまでも沈んでいきそうなスライム乳の柔らかさとはまるで違う、どこか芯のあるしっかりとした弾力。
張りのある乳肉と乳肉の間に挟まれたオスの象徴は、まだ挟んだだけなのにジンジンと根元から熱くなってしまったのです。
「全然違うでしょ?お姉ちゃんのペラペラでダルンダルンなおっぱいじゃ、この感じは無理…ですよね?」
敬語とタメ口を織り交ぜた独特の口調で問う凛子の瞳には、先ほどの恭子に負けず劣らずの魔性の光が宿っていました。
身長に比例した長い舌が、心臓をキュッと締め付けるほどの色香を湛えています。凛子は私がごくりと生唾を呑み込んだのを確認すると、妖しげな笑みを浮かべて横乳をグイグイと押し始めました。
「うっ…くぅう…」
私は恥ずかしながら、妻の若い頃の乳肉を思い出してしまいました。弾力のある乳房は上下にこき上げるまでもなく肉棒を跳ね返し、極上の感触でマッサージを繰り出します。
妻も出産する前はこれに近い弾力を誇っていましたが、正直なところ過去の妻よりも凛子の方が勝っているといわざるを得ません。
私の反応を凛子の横で窺っている妻の顔に、焦りと悔しさが滲んでいきます。皮肉なことに、パイズリに圧倒的な自信を持っている妻のそんな表情がマラ棒をさらに熱くするのでした。
「お兄さんのオチンチン、すっごく硬いですね。あんっ…私まで熱くなってきちゃった…んっ…はあっ…」
凛子が首を振ってオレンジブラウンのセミロングを払うと、汗が浮かんだ首筋が露になります。極上ボディのうら若き乙女が自分の肉棒を挟み込み、昂っているのを目の前にして平常な気持ちを保てというのは無理な話です。
すでにギンギンに漲っていた私のオス肉が、海綿体の膨張を最大まで強めていきます。それを見計らっていたかのように、凛子はくびれた腰を上下に動かして、Jカップ爆乳全体で私の肉棒を悦楽の布団で包み込みました。
「出しちゃっていいんですよ?お兄さんの濃いザーメン、私に飲ませて?」
上目遣いの凛子の瞳が潤み、物欲しげにパクパクと口を動かして私を挑発します。学生時代は奥手で、大学生になってもまともな恋愛ができないと恭子に相談していた初心な少女は、艶めかしい表情で男を惑わす女になっていました。
「うっ…ああっ!もう…だめだ…出るっ…」
心臓が早鐘を打ち始めて数秒にも満たないうちに、海綿体が爆発しそうな勢いでオスの昂ぶりが襲来しました。張りの強い乳房に揉まれた心地良さは、我慢の文字を私の辞書から取り去ってしまったようです。
どぴゅっと舞い上がる白濁の液体は凛子の鼻先をかすめ、小麦色の乳肉や顔面に降り注ぎました。
「あんっ…すっごーい。んちゅっ…れろおお…。2回目なのにたっぷり出ましたね。そんなに私のパイズリ、気持ち良かったですか?」
凛子は顔面や乳房を汚したオスの絶頂汁に構うことなく、愚息の亀頭にまとわりついた白濁のヴェールを舌で絡め取りました。舌先が鈴口を突きまわすと、
「うぅ…凛子ちゃん…そこは…」
腰が浮き上がりそうな快感に呻いてしまいます。これは口淫の方も相当できるに違いないとふしだらな想像が私の脳裏を過ったそのとき、妻の鋭い声が耳に届きました。
「そこまでよ。凛子、シン君から離れなさい」
「んちゅっ…。お姉ちゃんだってオチンチン舐めてたのに、ずるいですよねえ?」
凛子は文句を垂れながらも素直に身を引き、Jカップ爆乳の圧迫を解きました。長い間背負っていた重い荷物を下ろしたときのような開放感が物語るのは、凛子の乳房の弾力強さです。
ホッと息を吐く私でしたが、すぐに恭子のスライム乳が半勃ちにまで萎んでいた男根を包み込みました。
「シン君、まだまだ出るでしょ?だって昨日もいっぱい射精したもんね?」
煽るような言葉を吐く恭子でしたが、その声が若干震えていることに私は気づきました。これは夫婦だからこそわかる声色の変化です。そして私は、妻を不安にさせている原因についても心当たりがありました。
2回目の射精で放った私の精液が、いつも恭子のパイズリで出している量よりも遙かに多かったからです。私は妻の不安を少しでも和らげるために、
「ああ。頼むよ、恭子」
と言いながら彼女の頭を優しく撫でました。普段であれば目力の強い瞳で私を睨みつけながら、
「挟んでもらってる分際で生意気なことしないでくれる?」
と悪態をつくのですが、今日に限っては素直に頷いて、
「ありがとう。私、頑張るから…」
儚くも色気を携えた笑みを浮かべたのです。ひたむきな妻に奉仕させていることへの背徳感が、萎れかけの肉棒を見る見るうちに漲らせました。
私の昂ぶりを肌で感じ取った妻は、スライム乳をパン生地のように捏ねまわして艶めかしいマッサージを開始します。
「んっ…ふうっ…んぐっ…はあっ…」
妻は熱い吐息が亀頭を何度も撫でるほど息を荒らげながらも、私から目を離すことはありません。
すでに2度射精していることもあり、これまでよりも射精欲が沸き上がりにくくなっていることを承知のうえで、必死に奉仕をする恭子。
女神のような美貌と、カウパーや精液で汚された乳房の淫猥な光のコントラストは、1枚の写真に切り取りたいほど神々しく、鉄のように硬くなった愚息を翻弄します。
乳房の質で勝負していた凛子のそれとは違い、力の入れ加減や方向、柔肌の滑らせ方まで洗練された乳奉仕。
心臓がバクバクと小刻みなビートを刻みだし、玉袋がキュッとせり上がります。
しかし私の口元が歪むのを見るや否や、恭子はまたも焦らし始めるのです。
「だめ。まだだよ。凛子のときよりいっぱい出してくれないと…んっ…いやだから…」
そう言いながら妻は舌肉を伸ばすと、亀頭の先に触れる直前でチロチロと動かしました。パイズリ対決で舌奉仕をするのかいかがなものかと声を上げたそうにする凛子ですが、恭子の舌肉はまさにギリギリのラインで踏みとどまっています。
あの柔らかい肉塊がどれほどの快楽をもたらすのか知っている私は、無意識のうちに腰を動かしてしまいました。それも見事に見通していた恭子は、舌肉をするっと口内に戻すと、
「変態。もっと腰振らないと、ペロペロしてあげないんだから」
口の端を吊り上げながらスライム乳を肉棒にギュッと押し付けてきます。三十路を超えてもなお滑らかな触り心地をキープしている柔肌にギュッと包まれた私は、
「はあっ…はあっ…」
後で思い返しても赤面してしまう必死さで腰を動かしてしまうのでした。これではまさに、私を手玉に取ることに慣れた恭子の思う壺です。
恭子は私の腰振りとは正反対の動きで乳房をこき上げることで、通常のパイズリの2倍近い摩擦を男根に与えることに成功していました。
その快楽たるや、ジェットコースターも顔負けのスリリングな体験です。気持ち良すぎて怖いのに、絶対に途中下車することが許されていない悦楽特急。
「おっ…んぐっ…ああ゛っ…」
私自身は覚えていないのですが、妻によるとこんなにも情けない喘ぎを上げてしまっていたようです。ただし、全ての感覚が肉棒に集結したようなオーガズム体験だけは、いつでも思い出せるほど記憶に残っています。
鼻と口から同時に息を吐き、唾液を飛ばしてしまうほどオスの快楽に酔った私の股間から、噴水も顔負けの真っ白なシャワーが噴き上げました。
| ▼ | 人妻と従妹のおっぱい対決 to-to 19/8/27(火) 13:51 |
| Re(1):人妻と従妹のおっぱい対決 to-to 19/8/27(火) 14:00 |
| Re(2):人妻と従妹のおっぱい対決 to-to 19/8/27(火) 14:01 |
| Re(3):人妻と従妹のおっぱい対決 to-to 19/10/30(水) 16:26 |
| Re(4):人妻と従妹のおっぱい対決 to-to 19/10/30(水) 16:29 | ≪ |
| Re(5):人妻と従妹のおっぱい対決 to-to 19/10/30(水) 16:32 |
| Re(2):人妻と従妹のおっぱい対決 楽天松井裕と安楽の4 19/10/31(木) 19:38 |
| Re(1):人妻と従妹のおっぱい対決 ハンセン 19/8/30(金) 12:49 |
| Re(1):人妻と従妹のおっぱい対決 ミライボウル 19/9/8(日) 15:49 |
| Re(1):人妻と従妹のおっぱい対決 名無し 19/10/26(土) 17:05 |
235,948
禁止事項
- 誹謗・中傷・乱暴な言葉遣い
- 無神経なage行為・過度な連続投稿
- 対象者の名誉を傷つけるスキャンダル等
- 個人が特定できるような地域情報
- 18歳未満を対象とした(成人が未成年を相手にする犯罪に該当する)告白投稿
- 出会いを求める投稿