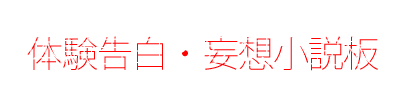
- 投稿される方は、無償且つ時間を掛けて文章を書き投稿されています。閲覧される方は、出来る限りお礼や感想(批判は×)を付けて頂けるようお願い致します。小説・体験投稿者のモチベーションを下げる返信等は削除、連投される場合はアクセス制限対応します。
- トピックの選択(特に、男性or女性、現実と妄想の区分けには御注意下さい)
- 投稿・返信は固定ハンドルネームでお願いします。
| ▼ | サーバ移転記念掌編です。 Angel Heart 20/10/11(日) 10:32 |
| Re:サーバ移転記念掌編です。 矜持衝突ファン 20/10/13(火) 18:29 |
| Re:サーバ移転記念掌編です。 Angel Heart 20/10/13(火) 19:09 |
| 妄想寄稿「妄想の宝箱」 AH凶 23/12/9(土) 13:01 |
| Re:妄想寄稿「妄想の宝箱」 Angel Heart 23/12/12(火) 17:35 |
| Re:妄想寄稿「妄想の宝箱」 fob@webmaster 23/12/13(水) 21:07 |
| Re:妄想寄稿「妄想の宝箱」 AH凶 23/12/14(木) 12:21 |
| Re:妄想寄稿「妄想の宝箱」 AH凶 23/12/14(木) 12:22 |
| Re: Angel Heart 23/12/15(金) 16:39 |
| Re: 純西別森木 25/1/12(日) 22:14 |
『異世界に召喚されたら囮にされていた件』
……気が付くとおれは両手足を縛られていた。ロープや粘着テープといった代物ではなく、うねうねと蠢く長い茎に。ちょうど蛇に全身を絡み取られる感じだ。
「ちょ……た、助けて」
「囮さんごめん。ウチら戦ってる暇ないのさ。モンスターの相手よろしく」
さっと敬礼すると四人組のパーティが駆け去っていった。辺りに漂うのは薄い霧。草いきれを放つ雑草は露に濡れている。どうやら朝の草原に横たわっているらしい。
「囮だけ召喚して逃げちゃった」
「しょうがないでしょ。私たちとお化けひまわり、倒してもたいした経験値にならないんだもん。あいつら結構なレベルだったよ。スルーされてよかったじゃん」
「勇者がスライムと出遭った感じかぁ」
顔立ちがそっくりな妖精が二匹、おれの頭上で舞っていた。虹色に輝く透明な羽を羽ばたかせ、蜂のようにホバリングしている。体長が15センチ程度しかないのに加え、美少女なのでモンスターとは思えなかった……って、痛い痛い痛い!
「お化けひまわりさん、絞め殺すのストップ。この人ただの囮だから」
シュゥゥゥゥ、と奇怪な唸り声をあげてお化けひまわりが束縛をとめた。種が生える部分――管状花に口だけがあり、茎葉を長い腕のように伸ばしておれを捕縛している。根を地面に埋めたまま歩けるらしい。きもかった。
「でも朝ごはんゲット」
と双子の片割れが喜んだ。カチューシャの色の違いでどちらか識別できる。
「朝ごはん……て? まさかお化けひまわりは人間を餌にしてるとかっ」
「違いますよ。囮さんに説明してあげるとですね、私たちは妖精族の亜種でフェラリーって言うんです。野宿してる旅人さんを襲って精子を吸い取る習性を持ってる。だから朝ごはんゲットなんです」
「蝶々が花の蜜を吸う、みたいな?」
「物分かりがいいですね。というわけで精子ごちそうになります」
双子がお化けひまわりに命令し、おれのパンツをズボンごと脱がせた。小さな身体では旅人の服を脱がせられないので、お化けひまわりと群れているという。服を脱がせてもらったお返しは、お化けひまわりの種をあちこちに撒くことだそうだ。
「待って。ち○ぽ見せるとか恥ずかしい」
「わお……この囮さん、包茎だ」
「おっきさせて早く皮をむくわよ」
白いカチューシャを着けた片割れが言い、おれの左脚の付け根に舞い降りた。もう一方のフェラリー――黄色いカチューシャを着けたほうは右脚の付け根に着地する。そして蝶々の口吻というか、蛇のような細長い舌を伸ばすと棒の裏をくすぐってきたのだった。
「……あひゃひゃひゃ。く、くすぐったいってば」
「気持ちいいみたいですね。そのまま勃起させちゃってください」
「ふにゃちんのままだと精子出してもらえなくて困るんです」
双子のちろちろフェラにおれは情けなくも勃起してしまった。ヌルヌルとした感触が肉棒を蠢くのだ。初フェラの相手は妖精です、とか妄想すぎてたまらない。
「これくらいで充分かな。よいしょ、と」「せーの、と」
フル勃起したち○ぽを、双子が倒れたポールを立てるように持ち上げる。阿吽の呼吸で包皮を下に引っ張られると亀頭全体が露出した。
「ちょっと囮さん。せっかく立てたんだからお腹にそり返らせないでください」
「そんなこと言っても気持ちいいし先っぽが爽快で」
無理やり立てられたちん○ぽは双子の背丈より若干低い。
「くんくん。このフェロモンの混じったおちんち○んのにおい。美味しそう」
「いただきまーす」
と二人が同時に舌を伸ばし、好き勝手にち○ぽを舐めはじめた。裏筋をちろちろとくすぐってはカリ首をなぞり、溝を丹念に擦る。尿道口に揃って舌を突っ込まれた時には悶絶するしかなかった。人間には真似できないフェラだ。
「やばひっ……出そうっ」
「出しちゃってください。顔に掛けられても平気ですよ」
片割れが尿道口をほじくり、もう片方が亀頭の扁平な部分を撫でる。途轍もない快感におれは精液を射出してしまった。飛び散った粘液に双子が夢中でくらいつく。
「おいっしいい! なにこれ最高の精子じゃん」
「ハァ〜〜……こういう精子を毎日食べられたらいいのに。絶品すぎて幸せ」
双子はヘソに着弾した精子、先っぽから滴る精子を次々と平らげていく。
「精子が絶品とか初めて言われたんだけど」
「精子の味はもちろん男性の数ほどありますよ。でもですね、やっぱり最高品質は高齢童貞なんです。熟成期間が違いますからね。満たされない性欲がなんともいえない風味を醸し出すんです」
褒められているような貶されているような。
双子の片割れがねだった。
「もっと精子ください。美味しすぎて食べ足りません」
「連射は大丈夫だけど思うけど……少ししか出ないかも」
「私たちがお手伝いします」
と目を輝かせてうなずくと、双子がすっぽんぽんになった。体長15センチしかないのに巨乳だとわかる。ま○こは種族特性なのか無毛だった。
「な、なにを……?」
「旅人さんを襲う時に使う得意技です。これをしてあげるとですね、初めは暴れてた旅人さんも喜んでくれるんですよ。おっぱいって種族が違っても男性の好物なんですよね」
言うや否や、萎える気配のないち○ぽを再び立たせ、双子が左右から抱きしめた。全裸でポールにしがみつくような格好だ。そして亀頭を舐めつつ身体を上下に動かす。小さな巨乳が肉棒を擦った。ちゃんとやわらかく弾力のあるおっぱいだった。
「くおおおっ……き、気持ちいい――っ」
「フェラリーの先天スキルです。おちん○ん、幸せでいっぱいになりません?」
四つの乳房が肉棒を圧迫する。絶妙な愛撫におれは射精欲をまた疼かせてしまった。現実の女性にパイズリフェラされるのも夢だが、妖精に弄ばれる喜びはたとえようがない。空っぽになったはずの精巣が充填されて、すぐに撒き散らしてしまった。
「結構出たじゃないですか」「飛びましたねえ」
(ハァハァ……き、気持ちよすぎるぞ、フェラリーのパイズリ)
「ああ美味しい。四つ星のおちん○んに出逢えて幸せ……はむっ、ちゅるちゅる」
「独り占めずるいよ! 私にも食べさせて」
きゃあきゃあと朝ごはんを取り合う双子の姿を、おれは恍惚とした心地で見守っていた。お化けひまわりに拘束されながら。
――そうして三発目をせがまれて果てた時、目の前には見慣れたおんぼろアパートが広がっていたのだった。
稀有な経験だった。パンツは異世界に置き忘れてきたらしいけど……まあいいか。
(おしまい)
……気が付くとおれは両手足を縛られていた。ロープや粘着テープといった代物ではなく、うねうねと蠢く長い茎に。ちょうど蛇に全身を絡み取られる感じだ。
「ちょ……た、助けて」
「囮さんごめん。ウチら戦ってる暇ないのさ。モンスターの相手よろしく」
さっと敬礼すると四人組のパーティが駆け去っていった。辺りに漂うのは薄い霧。草いきれを放つ雑草は露に濡れている。どうやら朝の草原に横たわっているらしい。
「囮だけ召喚して逃げちゃった」
「しょうがないでしょ。私たちとお化けひまわり、倒してもたいした経験値にならないんだもん。あいつら結構なレベルだったよ。スルーされてよかったじゃん」
「勇者がスライムと出遭った感じかぁ」
顔立ちがそっくりな妖精が二匹、おれの頭上で舞っていた。虹色に輝く透明な羽を羽ばたかせ、蜂のようにホバリングしている。体長が15センチ程度しかないのに加え、美少女なのでモンスターとは思えなかった……って、痛い痛い痛い!
「お化けひまわりさん、絞め殺すのストップ。この人ただの囮だから」
シュゥゥゥゥ、と奇怪な唸り声をあげてお化けひまわりが束縛をとめた。種が生える部分――管状花に口だけがあり、茎葉を長い腕のように伸ばしておれを捕縛している。根を地面に埋めたまま歩けるらしい。きもかった。
「でも朝ごはんゲット」
と双子の片割れが喜んだ。カチューシャの色の違いでどちらか識別できる。
「朝ごはん……て? まさかお化けひまわりは人間を餌にしてるとかっ」
「違いますよ。囮さんに説明してあげるとですね、私たちは妖精族の亜種でフェラリーって言うんです。野宿してる旅人さんを襲って精子を吸い取る習性を持ってる。だから朝ごはんゲットなんです」
「蝶々が花の蜜を吸う、みたいな?」
「物分かりがいいですね。というわけで精子ごちそうになります」
双子がお化けひまわりに命令し、おれのパンツをズボンごと脱がせた。小さな身体では旅人の服を脱がせられないので、お化けひまわりと群れているという。服を脱がせてもらったお返しは、お化けひまわりの種をあちこちに撒くことだそうだ。
「待って。ち○ぽ見せるとか恥ずかしい」
「わお……この囮さん、包茎だ」
「おっきさせて早く皮をむくわよ」
白いカチューシャを着けた片割れが言い、おれの左脚の付け根に舞い降りた。もう一方のフェラリー――黄色いカチューシャを着けたほうは右脚の付け根に着地する。そして蝶々の口吻というか、蛇のような細長い舌を伸ばすと棒の裏をくすぐってきたのだった。
「……あひゃひゃひゃ。く、くすぐったいってば」
「気持ちいいみたいですね。そのまま勃起させちゃってください」
「ふにゃちんのままだと精子出してもらえなくて困るんです」
双子のちろちろフェラにおれは情けなくも勃起してしまった。ヌルヌルとした感触が肉棒を蠢くのだ。初フェラの相手は妖精です、とか妄想すぎてたまらない。
「これくらいで充分かな。よいしょ、と」「せーの、と」
フル勃起したち○ぽを、双子が倒れたポールを立てるように持ち上げる。阿吽の呼吸で包皮を下に引っ張られると亀頭全体が露出した。
「ちょっと囮さん。せっかく立てたんだからお腹にそり返らせないでください」
「そんなこと言っても気持ちいいし先っぽが爽快で」
無理やり立てられたちん○ぽは双子の背丈より若干低い。
「くんくん。このフェロモンの混じったおちんち○んのにおい。美味しそう」
「いただきまーす」
と二人が同時に舌を伸ばし、好き勝手にち○ぽを舐めはじめた。裏筋をちろちろとくすぐってはカリ首をなぞり、溝を丹念に擦る。尿道口に揃って舌を突っ込まれた時には悶絶するしかなかった。人間には真似できないフェラだ。
「やばひっ……出そうっ」
「出しちゃってください。顔に掛けられても平気ですよ」
片割れが尿道口をほじくり、もう片方が亀頭の扁平な部分を撫でる。途轍もない快感におれは精液を射出してしまった。飛び散った粘液に双子が夢中でくらいつく。
「おいっしいい! なにこれ最高の精子じゃん」
「ハァ〜〜……こういう精子を毎日食べられたらいいのに。絶品すぎて幸せ」
双子はヘソに着弾した精子、先っぽから滴る精子を次々と平らげていく。
「精子が絶品とか初めて言われたんだけど」
「精子の味はもちろん男性の数ほどありますよ。でもですね、やっぱり最高品質は高齢童貞なんです。熟成期間が違いますからね。満たされない性欲がなんともいえない風味を醸し出すんです」
褒められているような貶されているような。
双子の片割れがねだった。
「もっと精子ください。美味しすぎて食べ足りません」
「連射は大丈夫だけど思うけど……少ししか出ないかも」
「私たちがお手伝いします」
と目を輝かせてうなずくと、双子がすっぽんぽんになった。体長15センチしかないのに巨乳だとわかる。ま○こは種族特性なのか無毛だった。
「な、なにを……?」
「旅人さんを襲う時に使う得意技です。これをしてあげるとですね、初めは暴れてた旅人さんも喜んでくれるんですよ。おっぱいって種族が違っても男性の好物なんですよね」
言うや否や、萎える気配のないち○ぽを再び立たせ、双子が左右から抱きしめた。全裸でポールにしがみつくような格好だ。そして亀頭を舐めつつ身体を上下に動かす。小さな巨乳が肉棒を擦った。ちゃんとやわらかく弾力のあるおっぱいだった。
「くおおおっ……き、気持ちいい――っ」
「フェラリーの先天スキルです。おちん○ん、幸せでいっぱいになりません?」
四つの乳房が肉棒を圧迫する。絶妙な愛撫におれは射精欲をまた疼かせてしまった。現実の女性にパイズリフェラされるのも夢だが、妖精に弄ばれる喜びはたとえようがない。空っぽになったはずの精巣が充填されて、すぐに撒き散らしてしまった。
「結構出たじゃないですか」「飛びましたねえ」
(ハァハァ……き、気持ちよすぎるぞ、フェラリーのパイズリ)
「ああ美味しい。四つ星のおちん○んに出逢えて幸せ……はむっ、ちゅるちゅる」
「独り占めずるいよ! 私にも食べさせて」
きゃあきゃあと朝ごはんを取り合う双子の姿を、おれは恍惚とした心地で見守っていた。お化けひまわりに拘束されながら。
――そうして三発目をせがまれて果てた時、目の前には見慣れたおんぼろアパートが広がっていたのだった。
稀有な経験だった。パンツは異世界に置き忘れてきたらしいけど……まあいいか。
(おしまい)
矜持衝突ファン
- 20/10/13(火) 18:29 -
おや!何やら荒れた痕跡がありましたので、遡ってみると先生の新作がありましたか!!
いやー、システムが新しくなって見やすくなったのか見にくくなったのか、慣れてないだけなのか分かりませんがなんとも言えないですね!
しかし、ファンタジーな淫夢もいいですね!
私も夢でいいのでフェラリー2人のダブル全身パイズリを受けてみたいです!!
いやー、システムが新しくなって見やすくなったのか見にくくなったのか、慣れてないだけなのか分かりませんがなんとも言えないですね!
しかし、ファンタジーな淫夢もいいですね!
私も夢でいいのでフェラリー2人のダブル全身パイズリを受けてみたいです!!
Angel Heart
- 20/10/13(火) 19:09 -
>矜持衝突ファンさん。
返信ありがとうございます。『サーバ移転』という題名が管理人さんによる事務報告と勘違いされたらしく、なかなかレスが来なくて落胆しているところでした。以前のようにタイトルが一行で収まる仕様であればちゃんとタイトルを書いたんですが。
フェラリーさんたちは以前から温めていたキャラです。作者が今後ファンタジー系の妄想小説を紡ぐことがあれば再登場するかもしれません。小さな巨乳で羽ばたく彼女たちを応援してあげてください。
「シュゥゥゥ――!」
あ、あともちろんお化けひまわりさんもです! 縛るのやめれっ――!
返信ありがとうございます。『サーバ移転』という題名が管理人さんによる事務報告と勘違いされたらしく、なかなかレスが来なくて落胆しているところでした。以前のようにタイトルが一行で収まる仕様であればちゃんとタイトルを書いたんですが。
フェラリーさんたちは以前から温めていたキャラです。作者が今後ファンタジー系の妄想小説を紡ぐことがあれば再登場するかもしれません。小さな巨乳で羽ばたく彼女たちを応援してあげてください。
「シュゥゥゥ――!」
あ、あともちろんお化けひまわりさんもです! 縛るのやめれっ――!
AH凶
- 23/12/9(土) 13:01 -
俺は22で、女子高生とラブホにいる。まさか、非モテの俺に声掛けなんて夢見てそうだ。丹波眞理子、名前だけでなく顔もかわいい、爆乳だ。「お兄さん、この部屋すごいよ」学校指定のスクールバッグを放り投げ、「ふかふか」と堪能する。その後、「おいで」と言われ、俺は直ぐさま眞理子の爆乳に顔を埋め、気持ち良いと呟く。「がっつき過ぎ、かわいい」。そう言われたが、夢中で眞理子の爆乳に顔を埋め、股間を太ももに擦り付けた。「プハー」と顔を上げては、再び眞理子の爆乳に顔を埋めた。終わった後は、ごはん奢ったが、いい思い出が出来た。
Angel Heart
- 23/12/12(火) 17:35 -
>AH凶さん
(誤字はありますが)Angel Heart作品のキャラを流用するなら出典を明示してくれますか。二次作品を特に禁止するつもりはありません。創作上の普遍ルールを守って管理人さんに迷惑をかけないようにしましょう。
(誤字はありますが)Angel Heart作品のキャラを流用するなら出典を明示してくれますか。二次作品を特に禁止するつもりはありません。創作上の普遍ルールを守って管理人さんに迷惑をかけないようにしましょう。
fob@webmaster
- 23/12/13(水) 21:07 -
シチュエーションやキャラクターの引用など、二次創作に関して(原作者が認めている場合に限る)は、出典(元作品のURL等)を明らかにするようお願いします。
元記事を編集するか、編集出来ない場合は、同意する内容の返信を頂ければ、当方で追記いたします。
一週間以内にご対応頂けない場合は、こちらの判断で削除等の対応をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
元記事を編集するか、編集出来ない場合は、同意する内容の返信を頂ければ、当方で追記いたします。
一週間以内にご対応頂けない場合は、こちらの判断で削除等の対応をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
AH凶
- 23/12/14(木) 12:21 -
丹羽眞理子「巨乳の妹ができたんですが、なにか?」AngelHeart作品では、モブの噛ませ犬だが、こちらではヒロインに抜擢、肉付けし優しい少女にしました。編集はこれで良いですか?時間ないからこれでまとめます。不備があるなら運営様の方で編集追記お願い致します。
Angel Heart
- 23/12/15(金) 16:39 -
>AH凶さん
そんなに難しく捉えなくていいです。本文の文頭か文末に、『この小説はAngel Heart作品の二次創作です』と一言加えていただければ。要するに原作者が誰かわかればいいのです。
そんなに難しく捉えなくていいです。本文の文頭か文末に、『この小説はAngel Heart作品の二次創作です』と一言加えていただければ。要するに原作者が誰かわかればいいのです。
純西別森木
- 25/1/12(日) 22:14 -
聖ブレスト女学園の女子高生達が、25歳の男にチュッチュッチュッチュッとキス責めし頬にキスマークつけたり、25歳の男に「一週間も萌美先輩や彩世さんが爆乳を顔に押し当てる何でどんな徳を積んだの?」と谷間に顔を埋めて聞いたり代わり番こに抱きつく話書いてほしいです。
235,840
禁止事項
- 誹謗・中傷・乱暴な言葉遣い
- 無神経なage行為・過度な連続投稿
- 対象者の名誉を傷つけるスキャンダル等
- 個人が特定できるような地域情報
- 18歳未満を対象とした(成人が未成年を相手にする犯罪に該当する)告白投稿
- 出会いを求める投稿