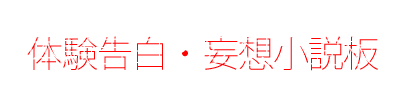
- 投稿される方は、無償且つ時間を掛けて文章を書き投稿されています。閲覧される方は、出来る限りお礼や感想(批判は×)を付けて頂けるようお願い致します。小説・体験投稿者のモチベーションを下げる返信等は削除、連投される場合はアクセス制限対応します。
- トピックの選択(特に、男性or女性、現実と妄想の区分けには御注意下さい)
- 投稿・返信は固定ハンドルネームでお願いします。
| ▼ | 巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運命を変えた上京〜 美脚巨乳が好き 15/12/2(水) 11:14 |
| Re(4):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... 美脚巨乳が好き 15/12/11(金) 13:02 |
| Re(5):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... ろくべえ 15/12/11(金) 21:45 |
| Re(6):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... 美脚巨乳が好き 15/12/11(金) 22:34 |
| Re(7):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... ろくべえ 15/12/11(金) 22:52 |
| Re(8):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... 藤浪柿田 15/12/12(土) 18:06 |
| Re(5):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... 美脚巨乳が好き 15/12/14(月) 12:04 |
| Re(6):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... ろくべえ 15/12/14(月) 21:39 |
| Re(7):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... 美脚巨乳が好き 15/12/14(月) 22:05 |
| Re(6):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... 美脚巨乳が好き 15/12/18(金) 16:00 |
| Re(7):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... ろくべえ 15/12/18(金) 22:42 |
| Re(8):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... 美脚巨乳が好き 15/12/18(金) 23:47 |
| Re(9):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... ろくべえ 15/12/19(土) 0:29 |
| Re(9):巨乳女子大生との出会いは突然に〜麻里子の運... 不死身の藤見る 18/11/24(土) 15:40 |
美脚巨乳が好き
- 15/12/11(金) 13:02 -
それは麻里子が自宅の最寄り駅に着いた時のことだった。
改札を出ると「麻里子さん」と呼ぶ声がする。
そこにはオタクっぽい中年男が立っていた。
するといきなり「私服も素敵ですね。普段もミニなんですか?」と一方的に話し始める。
麻里子がポカンとしていると、「今日、会場で見て写真を撮らせてもらって一発でファンになったんです」という。
でもなぜここに?
すると会場で麻里子に名前を尋ね、ブログを見たのだという。
麻里子はコンパニオンになってすぐ、事務所からブログやったらどう、と言われ毎日更新していたのだ。
でもどうしてここがわかったのか、麻里子は問い詰めた。
もしかしたらずっと自分の後をつけてきたんではないかと。
しかし理由は麻里子の不注意にあった。
数日前のブログに家の近くの行きつけです、とこの駅の近くのカフェをアップしていたのだ。
そしてブログの写真の周りの背景からここがわかったのだという。
また、今日は麻里子が仕事から帰ってくるときに必ずこの駅を通るから何時間もここで待っていたと。
「ファンになってくれるのはうれしいけどこんなこと、もうやめてください」と麻里子はきっぱりというと、男はおもむろにカメラを取り出し、そこに写っている一枚の写真を見せた。
それはイベントの時の麻里子のパンチラ写真だった。
しかも顔も映っている。
ただでさえ裾が短いミニワンピなのに、麻里子はその豊かな胸でぐっと押し上げるので余計短くなってしまい、少し前かがみになると中が見えそうな状態だった。
しかし初めての仕事で緊張していた麻里子にそれを気にする余裕などなかった。
それを逆手に取られ、前かがみになった瞬間を撮られてしまったのだ。
しかも悪いことにコスが白なのでピンクのショーツが鮮やかに写っている。
そして「これ、ネットにアップすることもできるんだけど」と麻里子を脅してきたのだ。
麻里子はまだこの仕事を始めたばかりだ。
こんな写真が出回ったらもう大変なことになる。
お金でかたをつけろということか、それとも・・・。
男は周りの目が気になったのか、小さな声で「やらせてくれとまではいわない。そのきれいな脚とでかい胸に触らせてくれればそれでいい」と少しやさしめにいうと、近くの駐車場に停めてある自分の車に麻里子を連れて行った。
そうはいってもいきなり襲ってこないとも限らない、何とかHだけはさせたくない、でもどうしよう、麻里子は様々な思いが頭をよぎった。
すると車に乗り込むや否や助手席のミニからむき出しになった麻里子の脚に触り始めたのだ。
麻里子は覚悟を決めた。
そして「今回だけですよ。そして終わったらそれ、消してくれるなら」と応諾した。
「きれいな脚だなー。もう脚だけでいきそうだよ」
ミニスカから麻里子の白くすらりと伸びた長い脚が街灯の薄明り越しに輝く。
その上を男のごわごわした手が動く。
「脚長いね。身長の半分脚みたいだ。会場でほかの子と並んでも断然腰の位置高いもん」
しかし麻里子は男と会話をする気など毛頭なかった。
「早く終わって。とにかく早く」麻里子は心の中で叫ぶ。
すると予想通りスカートの中に男の手が入る。
そして太ももをひとしきり撫でまわすと、今度はショーツにまで手をかけた。
それには麻里子が激しく抵抗すると意外とあっさりとあきらめ、今度はシャツ越しに胸を触る。
「大きいね。何カップ?」
しかしこんな男にブラのサイズを教える義理などない。
また下手に教えるとまたネットで書き込みされる可能性がある。
麻里子は聞こえないふりをした。
「これはGはあるな。コンパニオンってスタイルはいいけど胸ない子多いからな。脚はきれいだし乳はでかいし、もうたまんねーよ。いったい何を食ったらこんな体になるんだ」と独り言を言いながら服に手を入れ、ブラをずらして揉んでくる。
「でけーなー、この細い体にこの胸。恐ろしいバランスだな」といやらしくつぶやきながら男は「麻里子ちゃん、俺のモノをここに挟んでくれないか」とパイズリを懇願した。
Hやキスはいやだけど、パイズリならいいか。
そう思って「いいですよ」といい、男が自分のモノを出したその瞬間だった。
運転席を懐中電灯が照らし、ドアを叩く音がした。
警察だった。
「こんなところで何をしてるんだ」
二人の警察官は巡回中に車の中で二人が怪しい動きをしてるのに気が付き、近くに隠れて見張っていたのだ。
麻里子は男と引きはなされ、別々に事情を聞かれた。
麻里子はことの顛末をすべて正直に話した。
「それは男に脅されたから仕方なく応じたということですね」と警察官は麻里子に確認を取ると、男はあっさりと自供したため恐喝罪で逮捕された。
麻里子は触られはしたものの、間一髪のところで救われた。
これがきっかけで麻里子はコンパニオンの仕事を辞めた。
しかしイベント業界ではすい星のごとく現れ、そして消えていった美脚巨乳コンパニオンとして今も麻里子の名は語り継がれているのだ。
改札を出ると「麻里子さん」と呼ぶ声がする。
そこにはオタクっぽい中年男が立っていた。
するといきなり「私服も素敵ですね。普段もミニなんですか?」と一方的に話し始める。
麻里子がポカンとしていると、「今日、会場で見て写真を撮らせてもらって一発でファンになったんです」という。
でもなぜここに?
すると会場で麻里子に名前を尋ね、ブログを見たのだという。
麻里子はコンパニオンになってすぐ、事務所からブログやったらどう、と言われ毎日更新していたのだ。
でもどうしてここがわかったのか、麻里子は問い詰めた。
もしかしたらずっと自分の後をつけてきたんではないかと。
しかし理由は麻里子の不注意にあった。
数日前のブログに家の近くの行きつけです、とこの駅の近くのカフェをアップしていたのだ。
そしてブログの写真の周りの背景からここがわかったのだという。
また、今日は麻里子が仕事から帰ってくるときに必ずこの駅を通るから何時間もここで待っていたと。
「ファンになってくれるのはうれしいけどこんなこと、もうやめてください」と麻里子はきっぱりというと、男はおもむろにカメラを取り出し、そこに写っている一枚の写真を見せた。
それはイベントの時の麻里子のパンチラ写真だった。
しかも顔も映っている。
ただでさえ裾が短いミニワンピなのに、麻里子はその豊かな胸でぐっと押し上げるので余計短くなってしまい、少し前かがみになると中が見えそうな状態だった。
しかし初めての仕事で緊張していた麻里子にそれを気にする余裕などなかった。
それを逆手に取られ、前かがみになった瞬間を撮られてしまったのだ。
しかも悪いことにコスが白なのでピンクのショーツが鮮やかに写っている。
そして「これ、ネットにアップすることもできるんだけど」と麻里子を脅してきたのだ。
麻里子はまだこの仕事を始めたばかりだ。
こんな写真が出回ったらもう大変なことになる。
お金でかたをつけろということか、それとも・・・。
男は周りの目が気になったのか、小さな声で「やらせてくれとまではいわない。そのきれいな脚とでかい胸に触らせてくれればそれでいい」と少しやさしめにいうと、近くの駐車場に停めてある自分の車に麻里子を連れて行った。
そうはいってもいきなり襲ってこないとも限らない、何とかHだけはさせたくない、でもどうしよう、麻里子は様々な思いが頭をよぎった。
すると車に乗り込むや否や助手席のミニからむき出しになった麻里子の脚に触り始めたのだ。
麻里子は覚悟を決めた。
そして「今回だけですよ。そして終わったらそれ、消してくれるなら」と応諾した。
「きれいな脚だなー。もう脚だけでいきそうだよ」
ミニスカから麻里子の白くすらりと伸びた長い脚が街灯の薄明り越しに輝く。
その上を男のごわごわした手が動く。
「脚長いね。身長の半分脚みたいだ。会場でほかの子と並んでも断然腰の位置高いもん」
しかし麻里子は男と会話をする気など毛頭なかった。
「早く終わって。とにかく早く」麻里子は心の中で叫ぶ。
すると予想通りスカートの中に男の手が入る。
そして太ももをひとしきり撫でまわすと、今度はショーツにまで手をかけた。
それには麻里子が激しく抵抗すると意外とあっさりとあきらめ、今度はシャツ越しに胸を触る。
「大きいね。何カップ?」
しかしこんな男にブラのサイズを教える義理などない。
また下手に教えるとまたネットで書き込みされる可能性がある。
麻里子は聞こえないふりをした。
「これはGはあるな。コンパニオンってスタイルはいいけど胸ない子多いからな。脚はきれいだし乳はでかいし、もうたまんねーよ。いったい何を食ったらこんな体になるんだ」と独り言を言いながら服に手を入れ、ブラをずらして揉んでくる。
「でけーなー、この細い体にこの胸。恐ろしいバランスだな」といやらしくつぶやきながら男は「麻里子ちゃん、俺のモノをここに挟んでくれないか」とパイズリを懇願した。
Hやキスはいやだけど、パイズリならいいか。
そう思って「いいですよ」といい、男が自分のモノを出したその瞬間だった。
運転席を懐中電灯が照らし、ドアを叩く音がした。
警察だった。
「こんなところで何をしてるんだ」
二人の警察官は巡回中に車の中で二人が怪しい動きをしてるのに気が付き、近くに隠れて見張っていたのだ。
麻里子は男と引きはなされ、別々に事情を聞かれた。
麻里子はことの顛末をすべて正直に話した。
「それは男に脅されたから仕方なく応じたということですね」と警察官は麻里子に確認を取ると、男はあっさりと自供したため恐喝罪で逮捕された。
麻里子は触られはしたものの、間一髪のところで救われた。
これがきっかけで麻里子はコンパニオンの仕事を辞めた。
しかしイベント業界ではすい星のごとく現れ、そして消えていった美脚巨乳コンパニオンとして今も麻里子の名は語り継がれているのだ。
ろくべえ
- 15/12/11(金) 21:45 -
くぅ〜!いいところで警察!しかし、興奮しました!
そんなファンがいてもおかしくないですよね。
麻里子さんがパイズリを知っていたのが、また興奮しました。
警察の方はどこまで麻里子さんの体を見ていたのでしょう。
胸の一部が見えていたら…自分ならオカズにしちゃいますよ。
次なる展開も楽しみにしています。
そんなファンがいてもおかしくないですよね。
麻里子さんがパイズリを知っていたのが、また興奮しました。
警察の方はどこまで麻里子さんの体を見ていたのでしょう。
胸の一部が見えていたら…自分ならオカズにしちゃいますよ。
次なる展開も楽しみにしています。
美脚巨乳が好き
- 15/12/11(金) 22:34 -
>ろくべえさん
エロチックというよりエキサイティングな展開で、あまりここの掲示板にはふさわしくないストーリーになってしまったかもしれません。
しかし実際に撮影会の帰りに会場の最寄り駅でモデルを待ち伏せするやつがいるという話はあるらしいですよ。
エロチックというよりエキサイティングな展開で、あまりここの掲示板にはふさわしくないストーリーになってしまったかもしれません。
しかし実際に撮影会の帰りに会場の最寄り駅でモデルを待ち伏せするやつがいるという話はあるらしいですよ。
ろくべえ
- 15/12/11(金) 22:52 -
エキサイティングな展開、歓迎です!
次はどんなバイトか?あるいはサークルか?ゼミか?
いろいろ妄想してしまいます!
撮影会の帰りの待ち伏せ…そういうのも実際あるのですね。
やらせてくれとはいわないけれど…という気持ちはわかります!
次はどんなバイトか?あるいはサークルか?ゼミか?
いろいろ妄想してしまいます!
撮影会の帰りの待ち伏せ…そういうのも実際あるのですね。
やらせてくれとはいわないけれど…という気持ちはわかります!
美脚巨乳が好き
- 15/12/14(月) 12:04 -
やがて夏が過ぎ、秋を迎え学園祭のシーズンになった。
学園祭といえばミスコン。
そう、ミスキャンパスの座をかけ女子大生がしのぎを削る、容姿に自信がある女の子にとっては晴れ舞台であり、そして戦場だ。
特にA大のミスコンは女子アナやモデルなど多くの有名人を送り出している業界も注目のミスコンなのだ。
麻里子にも実行委員の友達からの推薦で声がかかった。
恥ずかしいし少し躊躇はしたが出ることにした。
賞金や商品が豪華なこともあり、100人近くの応募があったが、麻里子は書類選考を楽々と通過し、本選の20人に残った。
本選は学祭の最終日。
麻里子は手持ちのミニの中でも一番短いひざ上20cmのスカートにGカップのバストを強調するピタッとした胸元の開いたシャツ。
「○番、1年生のT麻里子です。よろしくお願いします」
その一言だけで「あのミニの子いいな」「おっぱいでかいな」
麻里子はもはや観客の目をくぎ付けにしていた。
ところがその麻里子にもライバルがいた。
2年生で去年の準ミスのえりなだ。
身長は麻里子より低いものの、丸顔でくるくるとした大きな瞳のかわいい系のルックスに華奢な体から突き出したFカップの豊かな胸はなんとも男好きするタイプ。
そしてえりなはアナウンサーを目指していて、来年の就活のためには何としてもミスキャンパスの肩書が必要なのだ。
最終選考には麻里子とえりなを含め5人が残ったが、事実上、麻里子とえりなの一騎打ちとなった。
えりなも麻里子が最大のライバルであることは十分分かっていた。
そしてえりなは最終選考ではこれでもかと自慢の胸を強調するほとんどキャミのような露出の激しい服で勝負に出たのだ。
これには観客も「すげー、あれまじ狙ってるぜ」「胸で勝負か」と声が漏れた。
麻里子もえりなが胸で勝負してくるのはわかっていたので、夏用の胸元の大きく開いた服で立ち向かう。
「胸はいい勝負だな。脚の差で麻里子ちゃんかな」
「いややっぱえりなちゃんかわいいし」
会場の意見も真っ二つ。
そしてついに発表の時が来た。
選ばれたのは・・・・
学園祭といえばミスコン。
そう、ミスキャンパスの座をかけ女子大生がしのぎを削る、容姿に自信がある女の子にとっては晴れ舞台であり、そして戦場だ。
特にA大のミスコンは女子アナやモデルなど多くの有名人を送り出している業界も注目のミスコンなのだ。
麻里子にも実行委員の友達からの推薦で声がかかった。
恥ずかしいし少し躊躇はしたが出ることにした。
賞金や商品が豪華なこともあり、100人近くの応募があったが、麻里子は書類選考を楽々と通過し、本選の20人に残った。
本選は学祭の最終日。
麻里子は手持ちのミニの中でも一番短いひざ上20cmのスカートにGカップのバストを強調するピタッとした胸元の開いたシャツ。
「○番、1年生のT麻里子です。よろしくお願いします」
その一言だけで「あのミニの子いいな」「おっぱいでかいな」
麻里子はもはや観客の目をくぎ付けにしていた。
ところがその麻里子にもライバルがいた。
2年生で去年の準ミスのえりなだ。
身長は麻里子より低いものの、丸顔でくるくるとした大きな瞳のかわいい系のルックスに華奢な体から突き出したFカップの豊かな胸はなんとも男好きするタイプ。
そしてえりなはアナウンサーを目指していて、来年の就活のためには何としてもミスキャンパスの肩書が必要なのだ。
最終選考には麻里子とえりなを含め5人が残ったが、事実上、麻里子とえりなの一騎打ちとなった。
えりなも麻里子が最大のライバルであることは十分分かっていた。
そしてえりなは最終選考ではこれでもかと自慢の胸を強調するほとんどキャミのような露出の激しい服で勝負に出たのだ。
これには観客も「すげー、あれまじ狙ってるぜ」「胸で勝負か」と声が漏れた。
麻里子もえりなが胸で勝負してくるのはわかっていたので、夏用の胸元の大きく開いた服で立ち向かう。
「胸はいい勝負だな。脚の差で麻里子ちゃんかな」
「いややっぱえりなちゃんかわいいし」
会場の意見も真っ二つ。
そしてついに発表の時が来た。
選ばれたのは・・・・
ろくべえ
- 15/12/14(月) 21:39 -
青○学院大のミスコンを想像しちゃいました。
えりなちゃんとのおっぱい対決!興奮します!
えりなちゃんは、何かしら胸を使った誘惑を仕掛けたのか、対する
麻里子さんは、何かしらサービスを仕掛けたのか、その辺り気になります!
最終的な発表方法やその後の展開も楽しみです!よろしくお願いします!
えりなちゃんとのおっぱい対決!興奮します!
えりなちゃんは、何かしら胸を使った誘惑を仕掛けたのか、対する
麻里子さんは、何かしらサービスを仕掛けたのか、その辺り気になります!
最終的な発表方法やその後の展開も楽しみです!よろしくお願いします!
美脚巨乳が好き
- 15/12/18(金) 16:00 -
ミスキャンパスの座を射止めたのはえりなだった。
会場の一般来場者投票では麻里子が大きく上回ったものの、配点のウエイトの大きい審査員票でえりなが上回ったのだ。
しかしこれが物議をかもすことになった。
「おかしいよ、一般投票と結果が違いすぎる」
「なんか不自然だな。調べたほうがいいよ」
そんな意見に押されて、再調査を行った結果、とんでもない事実が発覚したのだ。
時は最終選考の前日にさかのぼる。
ファイナリストの出場者20人は翌日の本選の打ち合わせに集められ、それが終わったときのことだった。
解散してほかの出場者がその場を離れるのを見届けると、翌日の審査委員長である4年生の学生にえりなが「今日ご飯でもどうですかぁ」と甘ったるい声で誘いをかけた。
もちろん横にいた3年の副委員長にも。
「この二人を抑えればあの1年の子に勝てるわ」
えりなにとっては麻里子に勝つための計算づくの行動だった。
学校でも評判の容姿を持つえりなに誘われて断る男などいるはずもない。
二人は喜んで夕方、えりなを連れて大学近くの居酒屋へ向かった。
もちろんえりなは自慢の胸をこれでもかと強調した谷間もばっちりの服で出陣。
1対2とはいえ、えりなと飲める機会などそうあるものではない。
二人は舞い上がっていた。
やがて酔いが回ってきた二人はえりなの胸に話を振る。
「えりなちゃんってかわいいのに胸もすごいんだね」
まずは先輩の委員長が褒め上げると
「えーやだーおっぱい星人だぁ」とこの辺りはまるでキャバ嬢のように相手を傷つけずするりとかわす男慣れしたえりなの真骨頂だ。
しかしここで胸フェチの副委員長が「ねーえりなちゃんって何カップ?」と畳みかける。
「えー、覚えてないよ〜」とここでも逃げようとしたが二人して問い詰めると「今Fなんだけど最近、きついの。Gとかなるとあんまりないしどうしよう〜」と少しかわい子ぶるえりな。
これは巨乳の自分がさらに胸が大きくなっていることをアピールする、胸フェチにとっては殺し文句ともいえるセリフだ。
そのかわいいルックスと胸を武器に男性経験も豊富なえりなにとって、年上とはいえ女性経験の少ない大学生など赤子の手をひねるようなものだった。
もう二人はメロメロにされていた。
すると「ねーえりなちゃん、うちこの近くなんだけどで飲みなおさない?」
と横に座っていた委員長から声がかかった。
しかしえりなにとってこの二人と恋愛関係になりたい気持ちなどかけらもなかった。
ほしいのは明日のミスコンでの自分への投票、ただそれだけ。
いかにもと思われるのも嫌なので「えーちょっとー」と一応は逃げたが、「明日のミスコンを逃せばもう女子アナの夢は絶たれてしまうかも。絶対ミスになりたい」
その気持ちが勝ってしまったのだ。
でもHまでしたくない。
テレビ局の偉い人なら別だけどこの段階でやらせるなんてもったいない。
するとえりなは「ねーカラオケ行こうよ、なんか歌いたいの〜」と甘えた声で言い、二人を誘った。
ボックスならおっぱい触られるくらいで済むし。そっから誘われたら今日はダメな日なのって断ればいい、えりなはどこまでも計算高かった。
腰を折られた男たちは落ち込んだもの、もしかしてボックスならおっぱいだけでも、という気持ちもあり気を取り直してここから近いカラオケボックスへ向かった。
最初は歌っていた3人だったが、やがて委員長がえりなの腰に手を回し、酔いに任せて服の上からおっぱいを触り始めたのだ。
「やだ、ダメ」とえりなは笑いながらかわした後、ついに本音を出した。
「明日、あたしに入れてくれるんならいいよ」と。
しかし盛りのついた男がこの要求を拒めるはずなどなかった。
「あたりまえじゃん。絶対えりなちゃんだし」と言うと「うそー、打ち合わせの時もあの1年のスタイルのいい子の脚とか胸ばっか見てたじゃん」と明らかに麻里子を意識した発言。
「えっ、そんなことないよ。えりなちゃんのほうがかわいいし」というと「ほんと?じゃあ明日絶対だよ」と念を押すとえりなは自分で胸元を開いて男の手を自分のブラのところに持って行った。
「すげー、これがGカップだ」
男は興奮してブラをずりさげて生乳を揉み始めた。
「こんなでかい乳、初めてだよ。もうたまんねー」
すると後輩の副委員長も黙っていない。
「俺も次、やらせてくださいよ」と懇願し、チェンジ。
「これがあのえりなちゃんのおっぱいか。おれ、えりなちゃんでいつも一人Hしてんだよ。もう夢みたいだ」と恍惚の表情でもみまくる。
しかしボックスではここまでが限界だった。
そしてえりなはとどめの一言も忘れなかった。
「ほかの委員の子にもあたしに入れるように言っておいてね」
ほかの委員は1年生や2年生なので先輩の二人が言えば大丈夫だろう。
そこまでえりなは計算していたのだ。
やがて3人への事情聴取でこの事実が明らかになり、えりなのミスキャンパスの栄冠は取り消され、麻里子が繰り上げとなった。
そしてスキャンダル好きなマスコミもこの事実を報じ、
「A大ミスコンで不正」
「アナウンサー志望の女子大生、肉弾攻撃」
などと大きく取り上げられ、えりなは好奇の目に耐えられず、退学することとなった。
一方で繰り上がり当選となった麻里子にも
「ミスA大は雪国出身の色白美人」
くらいはまだいいとしても
「モデル並みの脚とグラドル並みのバストを併せ持つスーパーボディーのミスA大」
「細身の体に推定GカップのA大ミスキャンパス」などと明らかに麻里子の体に焦点を当てた取り上げ方が目立った。
こんな麻里子を生き馬の目を抜く芸能界がほっておくわけがなかった。
会場の一般来場者投票では麻里子が大きく上回ったものの、配点のウエイトの大きい審査員票でえりなが上回ったのだ。
しかしこれが物議をかもすことになった。
「おかしいよ、一般投票と結果が違いすぎる」
「なんか不自然だな。調べたほうがいいよ」
そんな意見に押されて、再調査を行った結果、とんでもない事実が発覚したのだ。
時は最終選考の前日にさかのぼる。
ファイナリストの出場者20人は翌日の本選の打ち合わせに集められ、それが終わったときのことだった。
解散してほかの出場者がその場を離れるのを見届けると、翌日の審査委員長である4年生の学生にえりなが「今日ご飯でもどうですかぁ」と甘ったるい声で誘いをかけた。
もちろん横にいた3年の副委員長にも。
「この二人を抑えればあの1年の子に勝てるわ」
えりなにとっては麻里子に勝つための計算づくの行動だった。
学校でも評判の容姿を持つえりなに誘われて断る男などいるはずもない。
二人は喜んで夕方、えりなを連れて大学近くの居酒屋へ向かった。
もちろんえりなは自慢の胸をこれでもかと強調した谷間もばっちりの服で出陣。
1対2とはいえ、えりなと飲める機会などそうあるものではない。
二人は舞い上がっていた。
やがて酔いが回ってきた二人はえりなの胸に話を振る。
「えりなちゃんってかわいいのに胸もすごいんだね」
まずは先輩の委員長が褒め上げると
「えーやだーおっぱい星人だぁ」とこの辺りはまるでキャバ嬢のように相手を傷つけずするりとかわす男慣れしたえりなの真骨頂だ。
しかしここで胸フェチの副委員長が「ねーえりなちゃんって何カップ?」と畳みかける。
「えー、覚えてないよ〜」とここでも逃げようとしたが二人して問い詰めると「今Fなんだけど最近、きついの。Gとかなるとあんまりないしどうしよう〜」と少しかわい子ぶるえりな。
これは巨乳の自分がさらに胸が大きくなっていることをアピールする、胸フェチにとっては殺し文句ともいえるセリフだ。
そのかわいいルックスと胸を武器に男性経験も豊富なえりなにとって、年上とはいえ女性経験の少ない大学生など赤子の手をひねるようなものだった。
もう二人はメロメロにされていた。
すると「ねーえりなちゃん、うちこの近くなんだけどで飲みなおさない?」
と横に座っていた委員長から声がかかった。
しかしえりなにとってこの二人と恋愛関係になりたい気持ちなどかけらもなかった。
ほしいのは明日のミスコンでの自分への投票、ただそれだけ。
いかにもと思われるのも嫌なので「えーちょっとー」と一応は逃げたが、「明日のミスコンを逃せばもう女子アナの夢は絶たれてしまうかも。絶対ミスになりたい」
その気持ちが勝ってしまったのだ。
でもHまでしたくない。
テレビ局の偉い人なら別だけどこの段階でやらせるなんてもったいない。
するとえりなは「ねーカラオケ行こうよ、なんか歌いたいの〜」と甘えた声で言い、二人を誘った。
ボックスならおっぱい触られるくらいで済むし。そっから誘われたら今日はダメな日なのって断ればいい、えりなはどこまでも計算高かった。
腰を折られた男たちは落ち込んだもの、もしかしてボックスならおっぱいだけでも、という気持ちもあり気を取り直してここから近いカラオケボックスへ向かった。
最初は歌っていた3人だったが、やがて委員長がえりなの腰に手を回し、酔いに任せて服の上からおっぱいを触り始めたのだ。
「やだ、ダメ」とえりなは笑いながらかわした後、ついに本音を出した。
「明日、あたしに入れてくれるんならいいよ」と。
しかし盛りのついた男がこの要求を拒めるはずなどなかった。
「あたりまえじゃん。絶対えりなちゃんだし」と言うと「うそー、打ち合わせの時もあの1年のスタイルのいい子の脚とか胸ばっか見てたじゃん」と明らかに麻里子を意識した発言。
「えっ、そんなことないよ。えりなちゃんのほうがかわいいし」というと「ほんと?じゃあ明日絶対だよ」と念を押すとえりなは自分で胸元を開いて男の手を自分のブラのところに持って行った。
「すげー、これがGカップだ」
男は興奮してブラをずりさげて生乳を揉み始めた。
「こんなでかい乳、初めてだよ。もうたまんねー」
すると後輩の副委員長も黙っていない。
「俺も次、やらせてくださいよ」と懇願し、チェンジ。
「これがあのえりなちゃんのおっぱいか。おれ、えりなちゃんでいつも一人Hしてんだよ。もう夢みたいだ」と恍惚の表情でもみまくる。
しかしボックスではここまでが限界だった。
そしてえりなはとどめの一言も忘れなかった。
「ほかの委員の子にもあたしに入れるように言っておいてね」
ほかの委員は1年生や2年生なので先輩の二人が言えば大丈夫だろう。
そこまでえりなは計算していたのだ。
やがて3人への事情聴取でこの事実が明らかになり、えりなのミスキャンパスの栄冠は取り消され、麻里子が繰り上げとなった。
そしてスキャンダル好きなマスコミもこの事実を報じ、
「A大ミスコンで不正」
「アナウンサー志望の女子大生、肉弾攻撃」
などと大きく取り上げられ、えりなは好奇の目に耐えられず、退学することとなった。
一方で繰り上がり当選となった麻里子にも
「ミスA大は雪国出身の色白美人」
くらいはまだいいとしても
「モデル並みの脚とグラドル並みのバストを併せ持つスーパーボディーのミスA大」
「細身の体に推定GカップのA大ミスキャンパス」などと明らかに麻里子の体に焦点を当てた取り上げ方が目立った。
こんな麻里子を生き馬の目を抜く芸能界がほっておくわけがなかった。
ろくべえ
- 15/12/18(金) 22:42 -
舞台裏ありがとうございます!
いやあ、審査委員長&副委員長がうらやましいです!
ギンギンになった状態の審査委員長&副委員長は、
そのカラオケ店でよく我慢できましたね。審査委員長&
副委員長視点でのスピンオフ作品も見てみたくなりました。
えりなちゃんもその容姿と頭脳ならグラビアアイドルなどで
活躍できそうですので、その後のえりなちゃんも気になります!
もちろん麻里子さんの芸能界進出も楽しみです!
いやあ、審査委員長&副委員長がうらやましいです!
ギンギンになった状態の審査委員長&副委員長は、
そのカラオケ店でよく我慢できましたね。審査委員長&
副委員長視点でのスピンオフ作品も見てみたくなりました。
えりなちゃんもその容姿と頭脳ならグラビアアイドルなどで
活躍できそうですので、その後のえりなちゃんも気になります!
もちろん麻里子さんの芸能界進出も楽しみです!
美脚巨乳が好き
- 15/12/18(金) 23:47 -
>ろくべえさん
この男二人のスピンオフというのは考えてもみませんでした。
そしてえりなも結構使える題材だと思うので、えりなのスピンオフというのも面白いかもしれません。
そうなると麻美のスピンオフとかどんどん出てきてもうきりがなくなりそうです。
この男二人のスピンオフというのは考えてもみませんでした。
そしてえりなも結構使える題材だと思うので、えりなのスピンオフというのも面白いかもしれません。
そうなると麻美のスピンオフとかどんどん出てきてもうきりがなくなりそうです。
ろくべえ
- 15/12/19(土) 0:29 -
すみません、興奮のあまり膨らめすぎてしまいました。
とりあえず、基本線である麻里子さんの活躍を楽しみに
しております。いよいよ抜いてあげる場面が…とか妄想
が膨らんでしまいます。
とりあえず、基本線である麻里子さんの活躍を楽しみに
しております。いよいよ抜いてあげる場面が…とか妄想
が膨らんでしまいます。
235,963
禁止事項
- 誹謗・中傷・乱暴な言葉遣い
- 無神経なage行為・過度な連続投稿
- 対象者の名誉を傷つけるスキャンダル等
- 個人が特定できるような地域情報
- 18歳未満を対象とした(成人が未成年を相手にする犯罪に該当する)告白投稿
- 出会いを求める投稿