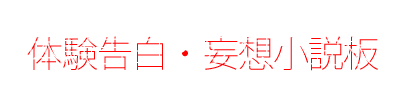
- 投稿される方は、無償且つ時間を掛けて文章を書き投稿されています。閲覧される方は、出来る限りお礼や感想(批判は×)を付けて頂けるようお願い致します。小説・体験投稿者のモチベーションを下げる返信等は削除、連投される場合はアクセス制限対応します。
- トピックの選択(特に、男性or女性、現実と妄想の区分けには御注意下さい)
- 投稿・返信は固定ハンドルネームでお願いします。
| ▼ | 巨乳女子高生みくの毎日 ぷりひろ 14/3/11(火) 16:08 |
| Re(18):巨乳女子高生みくの毎日 ぷりひろ 14/7/2(水) 15:21 |
| Re(19):巨乳女子高生みくの毎日 謝々 14/7/2(水) 19:57 |
| Re(20):巨乳女子高生みくの毎日 広島ノムケ 14/7/2(水) 22:34 |
| Re(21):巨乳女子高生みくの毎日 ぷりひろ 14/7/2(水) 22:42 |
| Re(20):巨乳女子高生みくの毎日 ぷりひろ 14/7/2(水) 22:41 |
| Re(21):巨乳女子高生みくの毎日 謝々 14/7/2(水) 22:51 |
| Re(19):巨乳女子高生みくの毎日 亀 14/7/5(土) 7:16 |
| Re(20):巨乳女子高生みくの毎日 ぷりひろ 14/7/11(金) 10:40 |
| Re(21):巨乳女子高生みくの毎日 藤見マン 14/11/28(金) 19:47 |
ぷりひろ
- 14/7/2(水) 15:21 -
みくの学校もついに夏休みに突入した。
好奇心いっぱいの女子高生にとって初めての夏休み。
何も起こらないはずがありません。
1年生なので補習もなく、休みに入ったすぐの日。
みくは登録してあるモデル事務所に呼び出されて行った。
するといつもの担当者ではなく登録の時に挨拶しただけの社長が出てきた。
今まで多くの売れっ子のキャンギャルやモデルを育ててきたこの業界では知らぬ人ない凄腕だ。
「みくちゃん、結構頑張ってるみたいだね。」
「あ、はい・・・」
「この間の撮影会でも好評だったらしいじゃないか。」
「あ、ありがとうございます」
「ところで、Sっていう雑誌知ってる?」
「はい、有名ですよね」
「うん、あれの表紙の子を今探してるんだ。どう?」
Sと言えば女の子なら知らない子はいないほど超メジャーなファッション雑誌。
それも表紙!
夢のような話です。
「でも私なんかで大丈夫ですか?」
「もし君がやる気があるなら話を通しておくから、向こうの出版社に面接に行く事になるよ」
「は、はいぜひお願いします」
と返事をするや否や、社長は携帯を手に取った。
「あ、編集長、いつもお世話になってます。Sの表紙の件、うちにぜひやりたいっていう子がいるんで会ってやっていただけませんでしょうか。この間入ったばっかりの子でまだ高1の子なんですけど、うちでも一押しなんです。本人もぜひやりたいって言ってますし。」
・・・
「あ、ありがとうございます。それでは明日の3時ですね。ちょっとお待ちください」
「明日3時でっておっしゃってるけど大丈夫?」
「はい」
「あ、結構です。ぜひよろしくお願いします。失礼いたします」
「よかったな、これが決まれば大変なことだ。くれぐれも編集長に失礼のないようにな」
「はい、ありがとうございます」
「明日はちょっと気合入れた衣装でね」
この一言でみくはピンときました。
翌日、みくは胸元の開いた露出多めの服に手持ちの中でも一番短いミニで出版社へ出かけました。
会社とはいってもファッション雑誌の出版社なのでモデルの女の子たちも頻繁に出入りしていて、きゃあきゃあとはしゃぐ声が飛び交い、まるで女子大か女子校の教室のようです。
編集長はみくのお父さんより明らかに年上で50くらいに見えました。
「やあ、きみか。昨日話には聞いてる。まあ入りなさい」
と応接室に通されました。
「君、背が高いね。何センチ?」
「166です」
「いつもミニが多いの?」
「はい、ほとんどミニです」
「ずいぶん脚長いね。股下は?」
「先月の登録の時に測ったら82でした」
「すごいね、ほとんど半分脚じゃないか。なかなか君レベルの子はいないよ」
「あ、そうですかぁ・・」
「スリーサイズは?」
「95、59、88です」
「へーすごいね、グラビアでもいけそうだ」
「ありがとうございます」
「ところでこれだけのルックスとスタイルだからぜひ君を推したいと思う。でも、他にも希望者が何人もいてね・・・」
こういわれるとみくの負けん気に火が付きます。
「ぜひお願いします。一生懸命やります」
「じゃあ、条件がある」
編集長はおもむろに立ち上がり、向かいに座っていたみくの隣に腰かけた。
そしてみくの顔を横から覗き込み、「分かるね」と確認するように言った。
みくは一瞬躊躇した。
すると「俺は実は乳フェチでね。モデルの子っていうのは細いのはいいんだけどどうも貧乳ばかりで物足りなくて。君みたいな巨乳の子がうちにもほしいよ」
といい、服の上から胸を揉み、上の開いた所から手を入れてきました。
「何カップ?」
「Gです」
「おー、Gなんか初めてだ。15歳の子の体とは思えないよ」
と言いながらつけていた黒のブラを外そうとします。
「でかいな」
「あ、あんまりかわいくなくて・・・」
「いいじゃないか。これがGカップか。若いから弾力も凄いな」
とひたすら胸に執着します。
みくはというと「Hとか言われたら今日はあの日だからダメってことにしよう。じゃあフェラとか言われるかも。キスは絶対断ろう」といろんな駆け引きが頭をめぐります。
そして編集長がにやけ顔でみくになにか話しかけようとした瞬間、部屋の内線電話が鳴ったのです。
明らかに不機嫌そうな編集長。
おもむろに受話器を取り「何だ!」と一言。
そして「分かった、すぐに下りる」といって電話を切った。
するとみくのほうを向き「決定でいいよ。お客さん来たみたいだからここまでだ」
ということでめでたく決定。
後日、担当者から電話があり、スタジオで撮影が行われ、翌月のSの表紙を飾ったのです。
その反響は半端なものではありませんでした。
「見たよ」というクラスメートからのメールや電話が殺到し、夏休み明けに学校へ行けば学校中の生徒からヒロイン扱い。
それどころかもはやみくはカリスマモデルにのし上がったのです。
好奇心いっぱいの女子高生にとって初めての夏休み。
何も起こらないはずがありません。
1年生なので補習もなく、休みに入ったすぐの日。
みくは登録してあるモデル事務所に呼び出されて行った。
するといつもの担当者ではなく登録の時に挨拶しただけの社長が出てきた。
今まで多くの売れっ子のキャンギャルやモデルを育ててきたこの業界では知らぬ人ない凄腕だ。
「みくちゃん、結構頑張ってるみたいだね。」
「あ、はい・・・」
「この間の撮影会でも好評だったらしいじゃないか。」
「あ、ありがとうございます」
「ところで、Sっていう雑誌知ってる?」
「はい、有名ですよね」
「うん、あれの表紙の子を今探してるんだ。どう?」
Sと言えば女の子なら知らない子はいないほど超メジャーなファッション雑誌。
それも表紙!
夢のような話です。
「でも私なんかで大丈夫ですか?」
「もし君がやる気があるなら話を通しておくから、向こうの出版社に面接に行く事になるよ」
「は、はいぜひお願いします」
と返事をするや否や、社長は携帯を手に取った。
「あ、編集長、いつもお世話になってます。Sの表紙の件、うちにぜひやりたいっていう子がいるんで会ってやっていただけませんでしょうか。この間入ったばっかりの子でまだ高1の子なんですけど、うちでも一押しなんです。本人もぜひやりたいって言ってますし。」
・・・
「あ、ありがとうございます。それでは明日の3時ですね。ちょっとお待ちください」
「明日3時でっておっしゃってるけど大丈夫?」
「はい」
「あ、結構です。ぜひよろしくお願いします。失礼いたします」
「よかったな、これが決まれば大変なことだ。くれぐれも編集長に失礼のないようにな」
「はい、ありがとうございます」
「明日はちょっと気合入れた衣装でね」
この一言でみくはピンときました。
翌日、みくは胸元の開いた露出多めの服に手持ちの中でも一番短いミニで出版社へ出かけました。
会社とはいってもファッション雑誌の出版社なのでモデルの女の子たちも頻繁に出入りしていて、きゃあきゃあとはしゃぐ声が飛び交い、まるで女子大か女子校の教室のようです。
編集長はみくのお父さんより明らかに年上で50くらいに見えました。
「やあ、きみか。昨日話には聞いてる。まあ入りなさい」
と応接室に通されました。
「君、背が高いね。何センチ?」
「166です」
「いつもミニが多いの?」
「はい、ほとんどミニです」
「ずいぶん脚長いね。股下は?」
「先月の登録の時に測ったら82でした」
「すごいね、ほとんど半分脚じゃないか。なかなか君レベルの子はいないよ」
「あ、そうですかぁ・・」
「スリーサイズは?」
「95、59、88です」
「へーすごいね、グラビアでもいけそうだ」
「ありがとうございます」
「ところでこれだけのルックスとスタイルだからぜひ君を推したいと思う。でも、他にも希望者が何人もいてね・・・」
こういわれるとみくの負けん気に火が付きます。
「ぜひお願いします。一生懸命やります」
「じゃあ、条件がある」
編集長はおもむろに立ち上がり、向かいに座っていたみくの隣に腰かけた。
そしてみくの顔を横から覗き込み、「分かるね」と確認するように言った。
みくは一瞬躊躇した。
すると「俺は実は乳フェチでね。モデルの子っていうのは細いのはいいんだけどどうも貧乳ばかりで物足りなくて。君みたいな巨乳の子がうちにもほしいよ」
といい、服の上から胸を揉み、上の開いた所から手を入れてきました。
「何カップ?」
「Gです」
「おー、Gなんか初めてだ。15歳の子の体とは思えないよ」
と言いながらつけていた黒のブラを外そうとします。
「でかいな」
「あ、あんまりかわいくなくて・・・」
「いいじゃないか。これがGカップか。若いから弾力も凄いな」
とひたすら胸に執着します。
みくはというと「Hとか言われたら今日はあの日だからダメってことにしよう。じゃあフェラとか言われるかも。キスは絶対断ろう」といろんな駆け引きが頭をめぐります。
そして編集長がにやけ顔でみくになにか話しかけようとした瞬間、部屋の内線電話が鳴ったのです。
明らかに不機嫌そうな編集長。
おもむろに受話器を取り「何だ!」と一言。
そして「分かった、すぐに下りる」といって電話を切った。
するとみくのほうを向き「決定でいいよ。お客さん来たみたいだからここまでだ」
ということでめでたく決定。
後日、担当者から電話があり、スタジオで撮影が行われ、翌月のSの表紙を飾ったのです。
その反響は半端なものではありませんでした。
「見たよ」というクラスメートからのメールや電話が殺到し、夏休み明けに学校へ行けば学校中の生徒からヒロイン扱い。
それどころかもはやみくはカリスマモデルにのし上がったのです。
謝々
- 14/7/2(水) 19:57 -
続編ありがとうございます!いいところで、内線が入ってしまいましたね。残念。フェラをいただきたかったなあ。次は、クラスメートからオカズにされる話とか?期待しております。
ぷりひろ
- 14/7/2(水) 22:41 -
▼謝々さん:
>続編ありがとうございます!いいところで、内線が入ってしまいましたね。残念。フェラをいただきたかったなあ。次は、クラスメートからオカズにされる話とか?期待しております。
編集長、残念でした。
あと、女子高だからクラスメートにオカズにされることはないですよ(笑)
>続編ありがとうございます!いいところで、内線が入ってしまいましたね。残念。フェラをいただきたかったなあ。次は、クラスメートからオカズにされる話とか?期待しております。
編集長、残念でした。
あと、女子高だからクラスメートにオカズにされることはないですよ(笑)
ぷりひろ
- 14/7/2(水) 22:42 -
▼広島ノムケさん:
>みくが前出たさとしでも誰でも良いからパイずりでいかしたり、巨乳で顔を埋もれさして欲しい。
このパターンもいずれ出てくると思いますよ。
>みくが前出たさとしでも誰でも良いからパイずりでいかしたり、巨乳で顔を埋もれさして欲しい。
このパターンもいずれ出てくると思いますよ。
謝々
- 14/7/2(水) 22:51 -
そうですか…。なるほど。では、文化祭などのイベントで他校の男子からねらわれるとか?
編集長、おっきしたままの来客対応でたいへんでしょうね。何とかして抜いてもらえばよかったのに。
編集長、おっきしたままの来客対応でたいへんでしょうね。何とかして抜いてもらえばよかったのに。
ぷりひろ
- 14/7/11(金) 10:40 -
▼亀さん:
>長身フェチ&数字フェチ的には股下82はあり得ない数字じゃないので、ベスト数字ですね。
>ぷりひろさんの引き出しの多さに脱帽です。
ありがとうございます。
実は僕自身脚フェチなんで(笑)
>長身フェチ&数字フェチ的には股下82はあり得ない数字じゃないので、ベスト数字ですね。
>ぷりひろさんの引き出しの多さに脱帽です。
ありがとうございます。
実は僕自身脚フェチなんで(笑)
235,920
禁止事項
- 誹謗・中傷・乱暴な言葉遣い
- 無神経なage行為・過度な連続投稿
- 対象者の名誉を傷つけるスキャンダル等
- 個人が特定できるような地域情報
- 18歳未満を対象とした(成人が未成年を相手にする犯罪に該当する)告白投稿
- 出会いを求める投稿